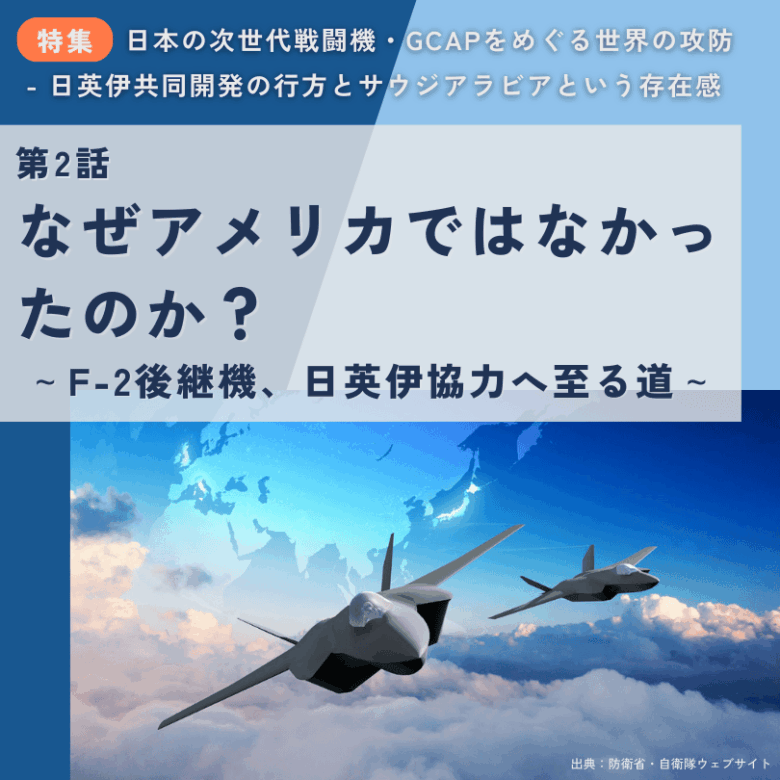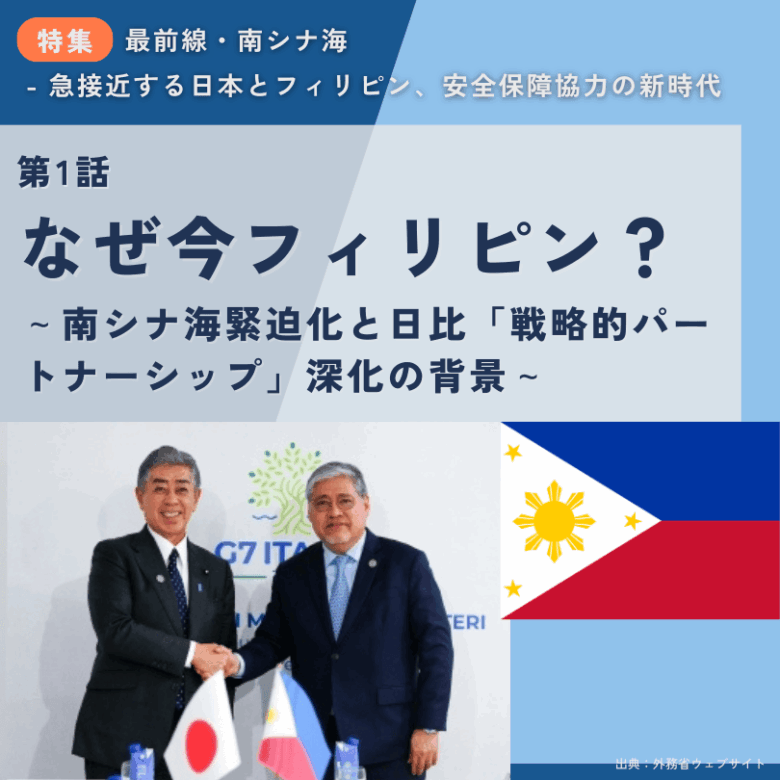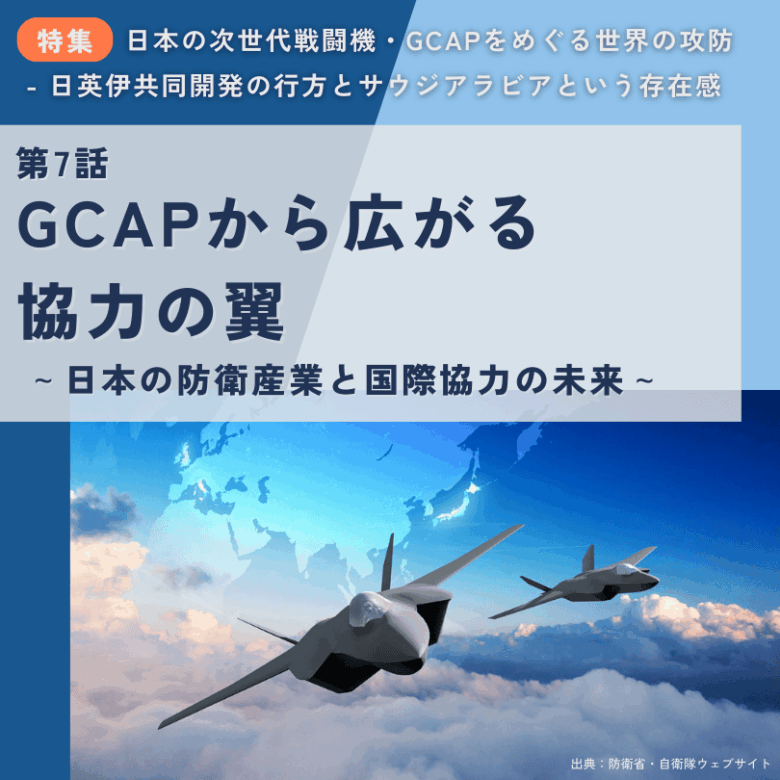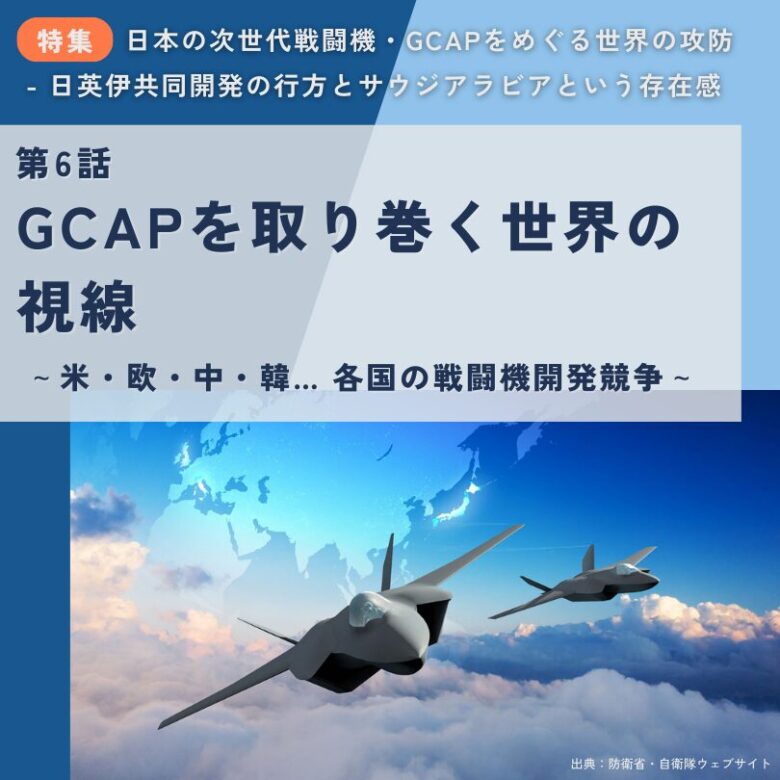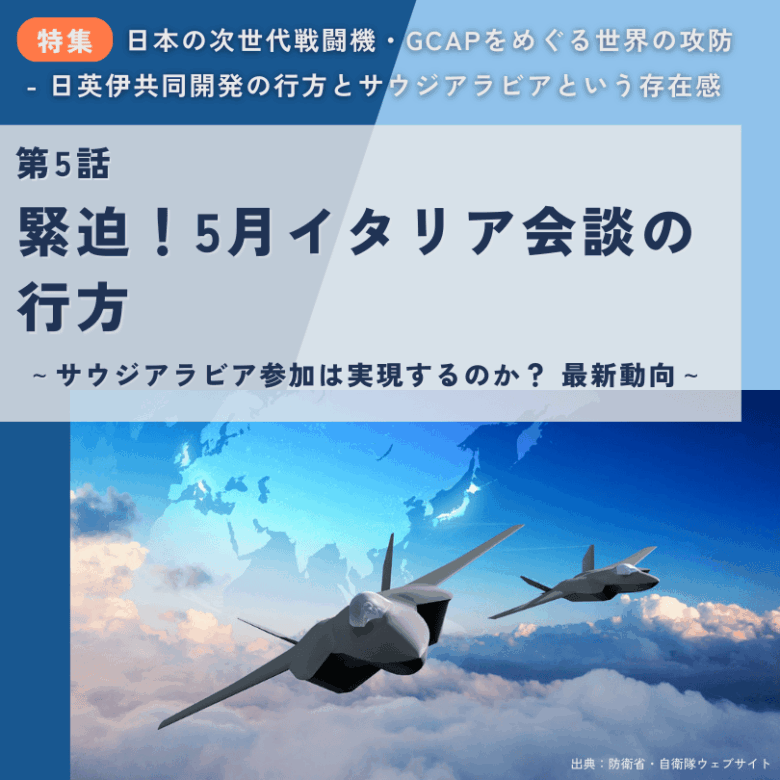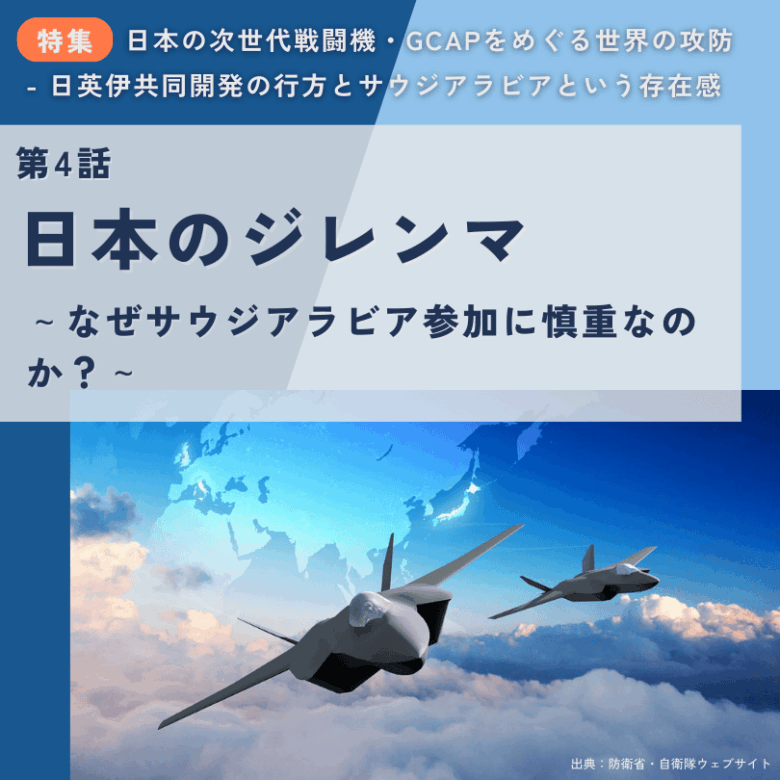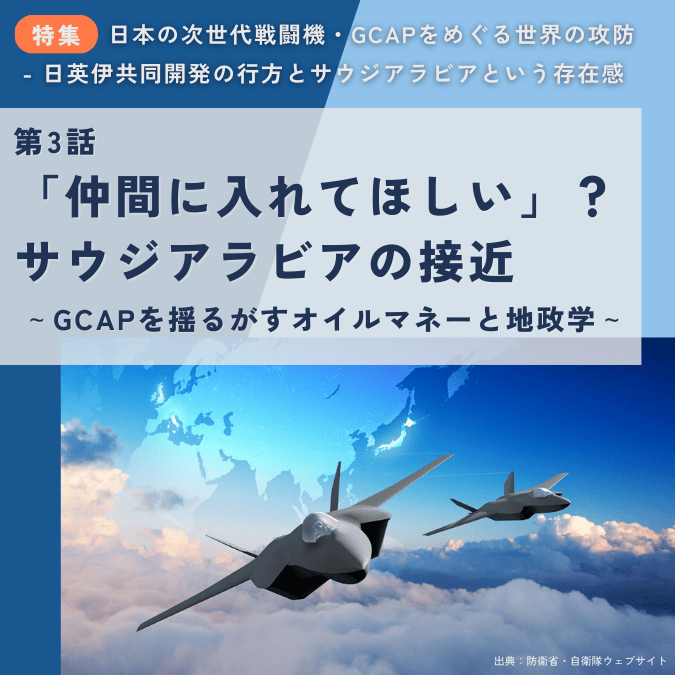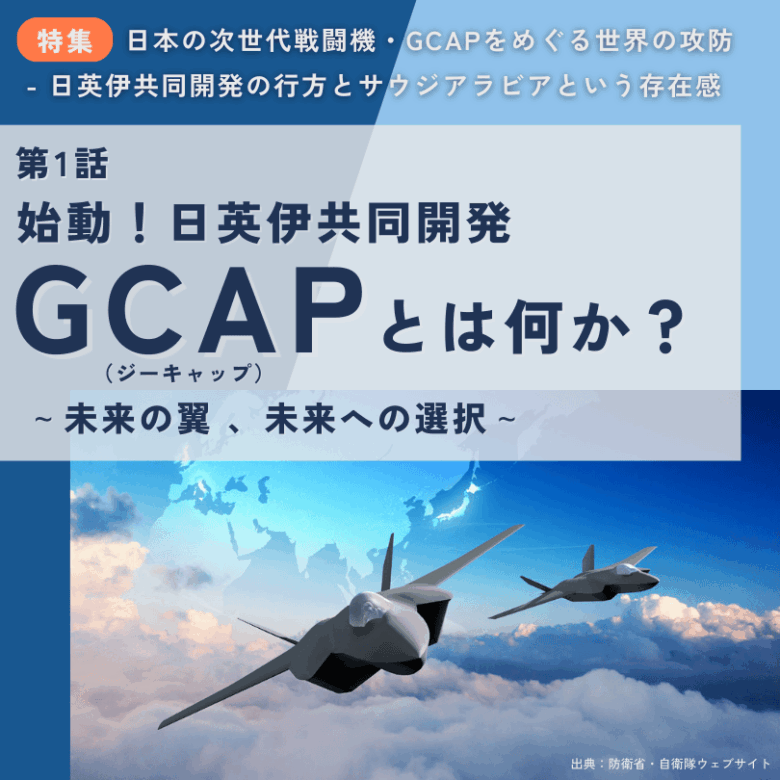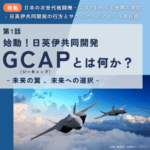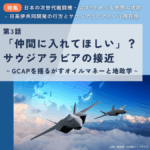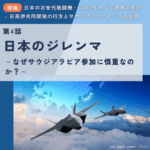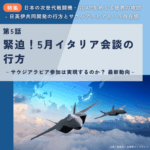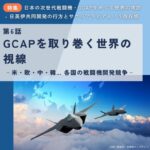第1話を読む
始動!日英伊共同開発「GCAP(ジーキャップ)」とは何か? ~未来の翼 、未来への選択~
【特集】
日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防
– 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感
第2話:なぜアメリカではなかったのか?
~F-2後継機、日英伊協力へ至る道~

前回は、日本、イギリス、イタリアが共同で開発を進める次世代戦闘機計画「GCAP」の概要と、それが目指す「第6世代」戦闘機の姿について解説しました。
この壮大なプロジェクトが正式に発表された際、多くの人が抱いた疑問があります。それは「なぜ、長年の同盟国であり、これまで戦闘機開発・導入で深い関係にあったアメリカと組まなかったのか?」ということです。
実際、航空自衛隊のF-2支援戦闘機の後継機(F-X)計画が始まった当初は、アメリカとの共同開発も有力な選択肢の一つとして検討されていました。しかし最終的に、日本はイギリス、イタリアとの協力、すなわちGCAPを選択しました。その決断の裏には、過去の経験から得た教訓と、日本の将来を見据えた戦略的な判断がありました。
過去の経験:F-2共同開発の「成功」と「教訓」
日本の戦闘機開発における日米協力の代表例といえば、F-2支援戦闘機です。これは、アメリカのF-16戦闘機をベースに、日本の運用要求に合わせて大幅な改造を施し、日米が共同で開発した機体です。

F-2開発は、当時の日本の技術を結集し、高性能な戦闘機を生み出すという点では「成功」でした。しかし同時に、いくつかの「教訓」も残しました。
- 開発の主導権
-
ベースが米国の機体であったため、開発プロセスにおいて米国側の意向が強く反映される場面が多くありました。
- 技術情報の開示制限
-
日本側が独自に開発した技術(高性能レーダーなど)を組み込んだ一方で、機体の根幹部分に関する重要な技術情報(特にソフトウェアの設計情報など、いわゆる「ブラックボックス」部分)については、米国側からの開示が制限されました。これにより、将来、日本が独自に機体を改修したり、能力を向上させたりする際に、自由度が制限されるという課題が残りました。
- コストの問題
-
当初の見込みよりも開発費が高騰したことも指摘されています。
これらの経験は、次のF-X計画を考える上で、日本にとって重要な判断材料となりました。
日本が求めた「開発の主導権」と「自由度」
F-2の後継機となるF-X計画において、日本政府と防衛省が最も重視したことの一つが、「開発の主導権を日本が握ること」そして「将来にわたって日本が自由に改修や能力向上を行えること」でした。
最先端の戦闘機は、導入して終わりではありません。技術の進歩に合わせてレーダーや電子機器を更新したり、新たな武器を搭載できるようにしたりと、常に能力を向上させていく必要があります。そのためには、機体の設計思想やソフトウェアの細部に至るまで、開発国自身が深く理解し、自由に手を加えられることが不可欠です。
アメリカとの共同開発も検討されましたが、F-2の経験を踏まえると、開発の主導権や将来の改修の自由度、そして核心的な技術情報の開示といった点で、日本側の要求を完全に満たすことが難しい可能性がありました。
イギリス・イタリアとの「対等なパートナーシップ」
そうした中で、有力なパートナーとして浮上したのが、イギリスとイタリアでした。
- 共通の目標
-
イギリスとイタリアも、同時期に次世代戦闘機の開発計画(テンペスト計画)を進めており、日本と技術的な目標や開発思想(将来の拡張性を重視する「オープンアーキテクチャ」など)で共通する部分が多くありました。
- 先行する技術協力
-
特にエンジン(日本のIHIとイギリスのロールス・ロイス)やセンサー技術などの分野では、日英間での共同研究が先行して進んでおり、協力関係の土台が築かれていました。
- 「対等なパートナーシップ」への期待
-
GCAPでは、日英伊が「対等なパートナー」として協力することが基本原則とされています。これにより、日本は開発プロセスに主体的に関与し、必要な技術情報へのアクセスや将来の改修の自由度を確保しやすいと期待されました。
- コスト効率
-
3カ国で開発費やリスクを分担することで、一国だけで開発するよりもコストを抑えられるというメリットもありました。
「米国離れ」ではない、戦略的な判断
このGCAP選択を、単純な「米国離れ」と見るのは正確ではありません。日米同盟は依然として日本の安全保障の基軸であり、その重要性に変わりはありません。
今回の選択は、あくまで「次期戦闘機開発」という特定のプロジェクトにおいて、日本の国益(技術的・産業的な利益、将来の運用における自由度など)を最大化するために、現時点で最も適したパートナーとしてイギリスとイタリアを選んだ、という戦略的な判断の結果です。
さらに、この選択には、日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」構想との関連も見逃せません。法の支配や民主主義といった価値観を共有する欧州の主要国(イギリス、イタリア)との安全保障協力を強化することは、FOIPの実現に向けた国際的な連携を多層的に進める上でも重要な意味を持つのです。これは、アメリカ一国に依存するのではなく、信頼できるパートナーを増やし、より安定した国際環境を築こうとする日本の姿勢の表れとも言えます。
まとめ
日本の次期戦闘機開発がGCAPへと舵を切った背景には、過去の教訓を踏まえた「自主性」と「自由度」の追求、そして日英伊3カ国の技術的・戦略的な利害の一致がありました。これは、変化する国際情勢の中で、日本が自らの国益と地域の安定のために下した、重要な選択と言えるでしょう。
しかし、この巨大な国際共同開発プロジェクトの道のりは、決して平坦ではありません。特に最近、新たな国の参加をめぐる動きが、GCAPの行方に大きな影響を与えようとしています。
次回は、特集の中心テーマである「サウジアラビア参加問題」に焦点を当て、なぜサウジアラビアがGCAPへの参加を望むのか、そしてそれに対して日英伊がどのような反応を示しているのか、その複雑な内情に迫ります。
第3話:「仲間に入れてほしい」? サウジアラビアの接近 ~GCAPを揺るがすオイルマネーと地政学~
画像出典:防衛省・自衛隊ウェブサイト(https://www.mod.go.jp/j/policy/defense/nextfighter/index.html)公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)
-

【特集:最前線・南シナ海 – 急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代】第2話:海を守る最前線 ~海上保安庁とフィリピン沿岸警備隊、長年の絆と奮闘~
-

【特集:最前線・南シナ海 – 急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代】第3話:陸海空で連携強化! ~自衛隊とフィリピン軍、共同訓練の拡大~
-

【特集:最前線・南シナ海 – 急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代】第1話:なぜ今フィリピン? ~南シナ海緊迫化と日比「戦略的パートナーシップ」深化の背景~
-

第7話:GCAPから広がる協力の翼 ~日本の防衛産業と国際協力の未来~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第6話:GCAPを取り巻く世界の視線 ~米・欧・中・韓… 各国の戦闘機開発競争~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第5話:緊迫!5月イタリア会談の行方 ~サウジアラビア参加は実現するのか? 最新動向~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第4話:日本のジレンマ ~なぜサウジアラビア参加に慎重なのか?~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第3話:「仲間に入れてほしい」? サウジアラビアの接近 ~GCAPを揺るがすオイルマネーと地政学~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第2話:なぜアメリカではなかったのか? ~F-2後継機、日英伊協力へ至る道~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第1話:始動!日英伊共同開発「GCAP(ジーキャップ)」とは何か? ~未来の翼 、未来への選択~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】