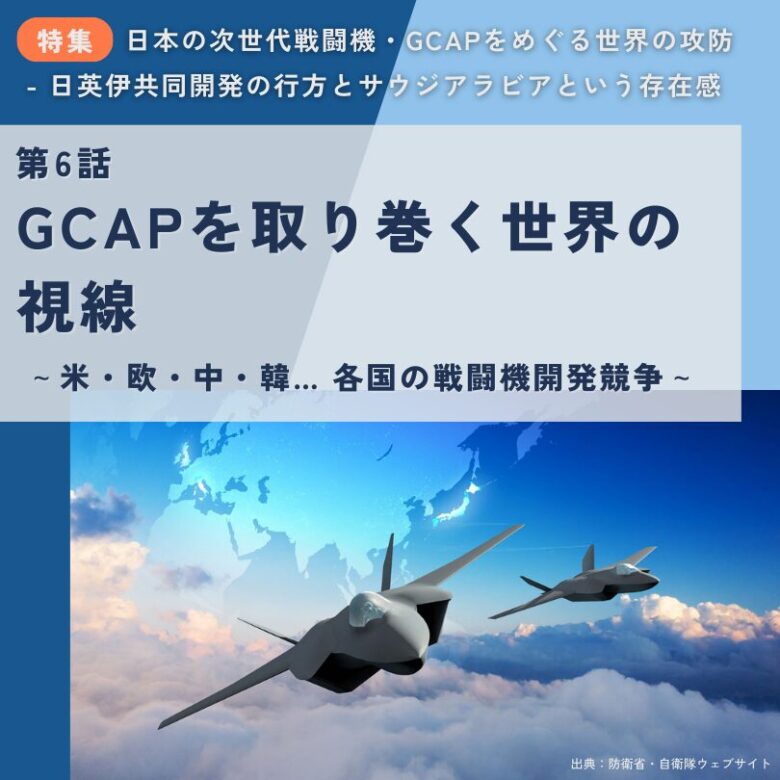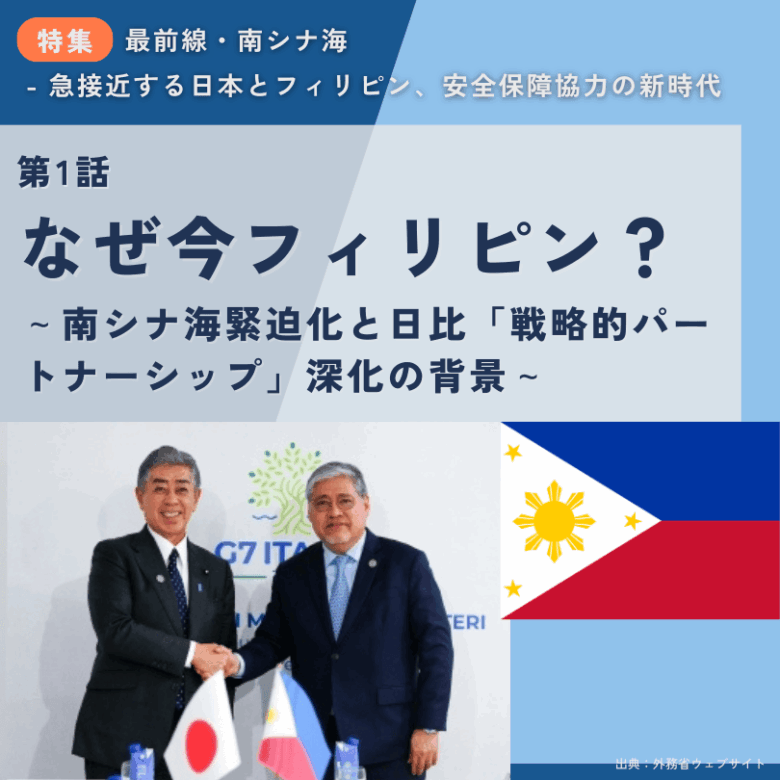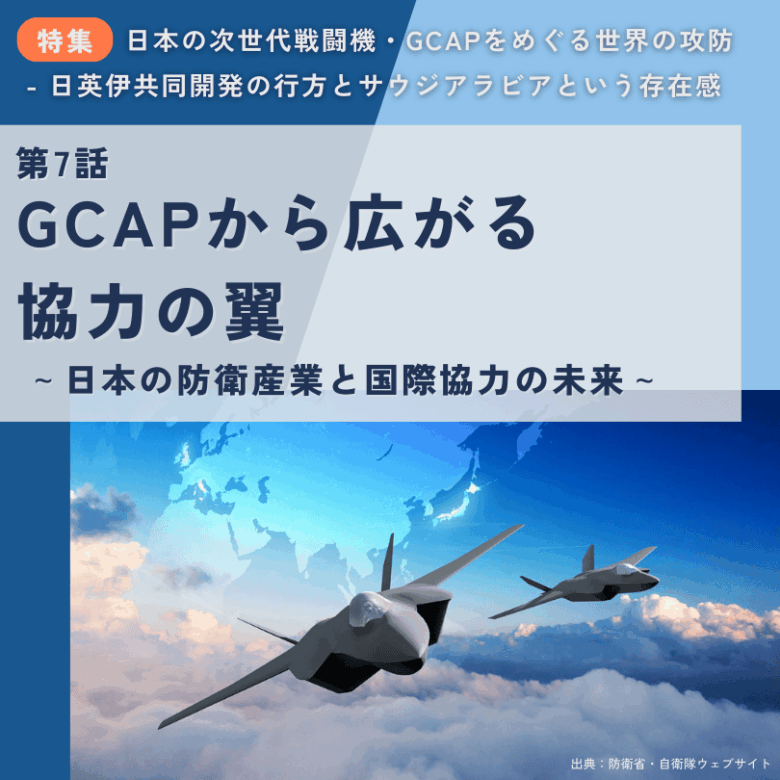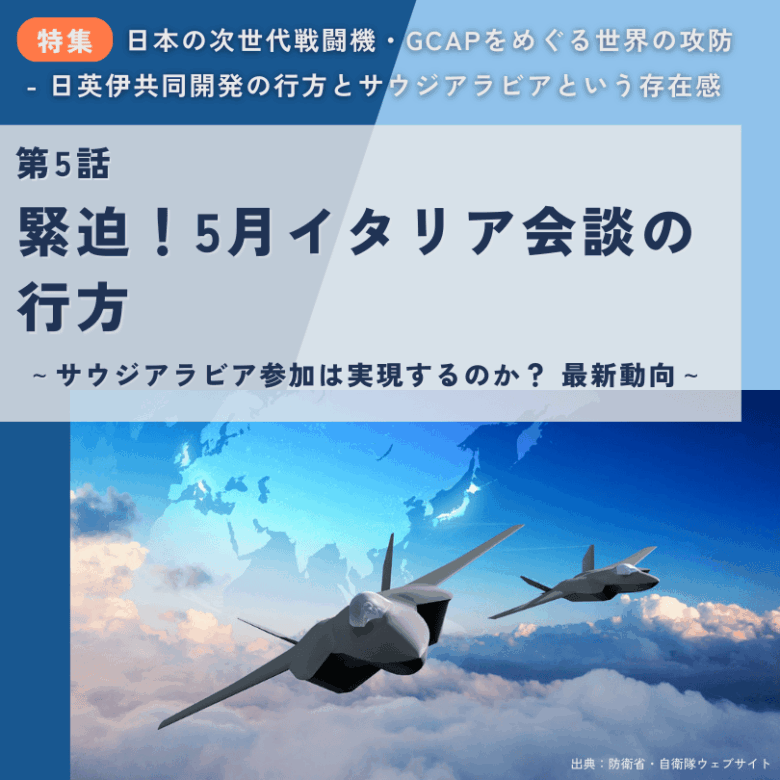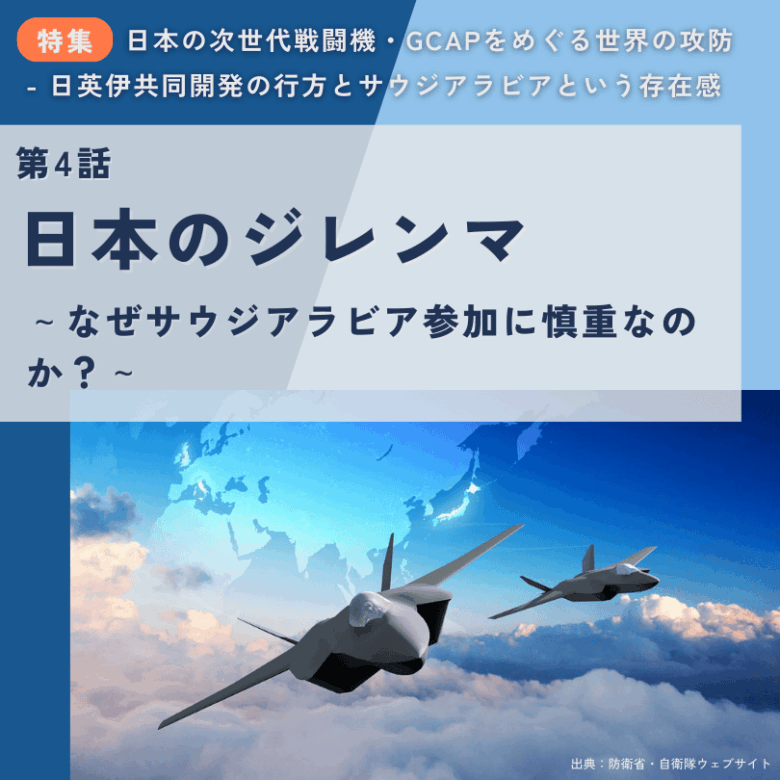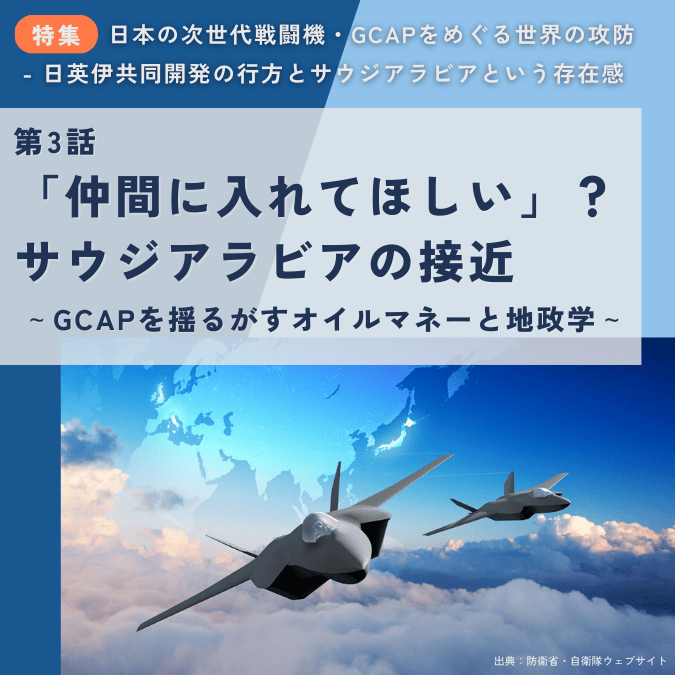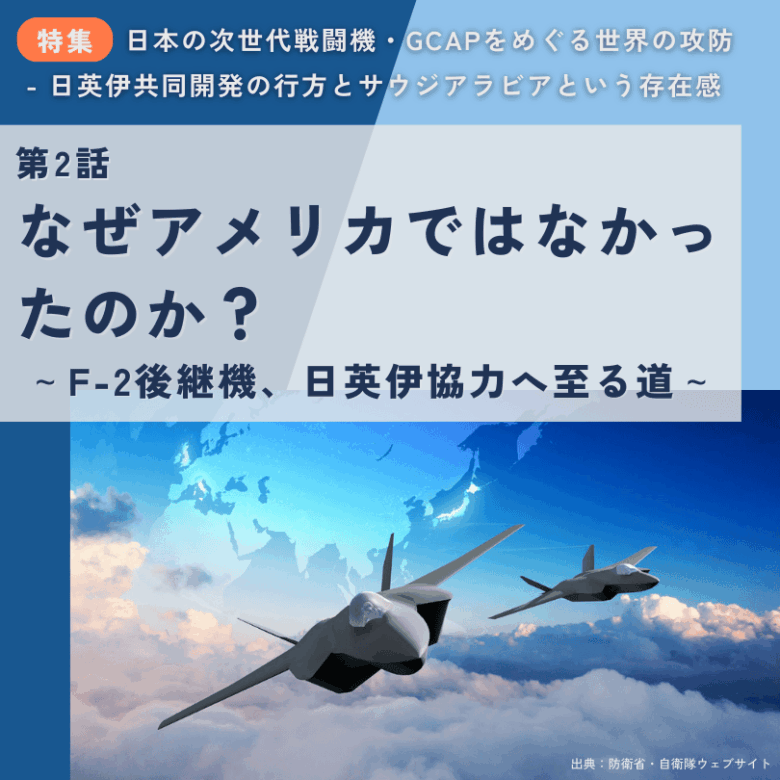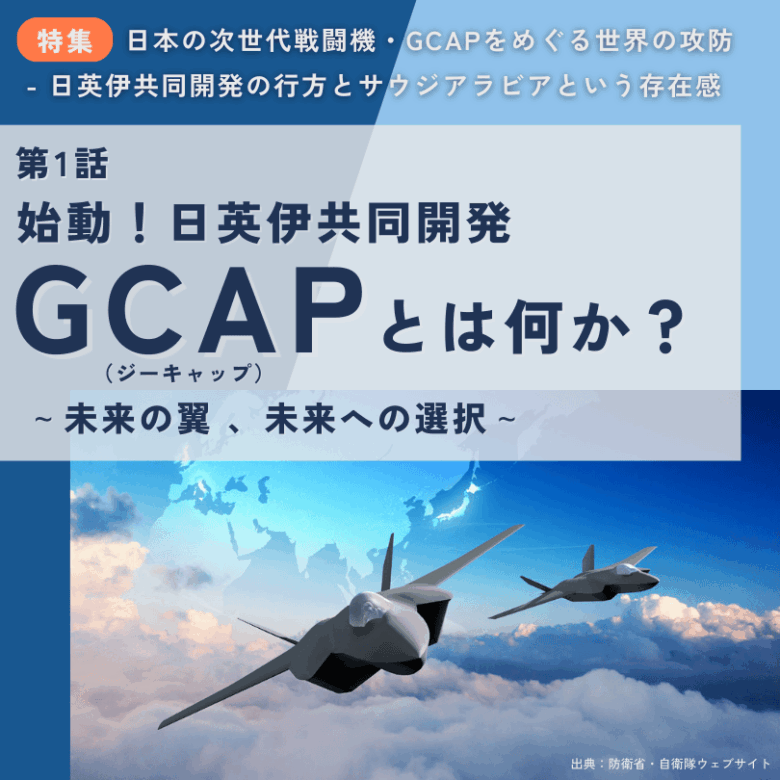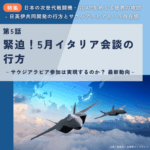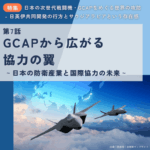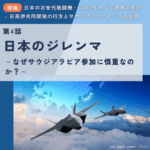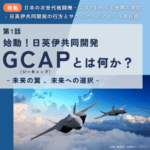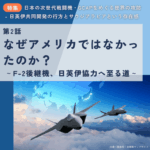第5話を読む
緊迫!5月イタリア会談の行方 ~サウジアラビア参加は実現するのか? 最新動向~
【特集】
日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防
– 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感
第6話:GCAPを取り巻く世界の視線
~米・欧・中・韓… 各国の戦闘機開発競争~

前回は、GCAP(次世代戦闘機共同開発計画)の今後を左右するかもしれない、5月に調整が進む日英伊(+サウジ?)防衛相会談に焦点を当てました。サウジアラビア参加問題という大きな課題を抱えつつも、プロジェクトは具体的な進展が模索されています。
さて今回は、少し視点をグローバルに広げてみましょう。日本、イギリス、イタリアがGCAPを進める一方で、世界各国も次世代の航空戦力を見据えた開発競争や戦略的な動きを活発化させています。GCAPは、こうした国際的な競争と協力の中で、どのような位置にあるのでしょうか?世界の主要プレイヤーの動向と、GCAPへの視線を見ていきましょう。
米国の「NGAD」:最大のパートナーであり、ライバル
GCAPを語る上で最も重要な存在が、同盟国アメリカが進める次世代戦闘機計画「NGAD(Next Generation Air Dominance:次世代航空支配)」です。
F-22戦闘機の後継を目指すこの計画も、GCAPと同様に、有人戦闘機と複数の無人機(僚機)、高度なネットワークなどを組み合わせた「システム」として構想されており、第6世代戦闘機のスタンダードを形作ると見られています。
アメリカはGCAP計画を公式に支持していますが、最も重視するのはGCAP戦闘機とNGADシステムが戦場でスムーズに連携できる「相互運用性」です。
共通の脅威に対処するためには、異なるシステム間でも情報共有や共同作戦が可能なことが不可欠だからです。このため、日米間などで緊密な技術的協議が行われていると考えられます。GCAPにとってNGADは、目標となる技術レベルを持つライバルであると同時に、連携が必須のパートナーでもあるのです。
欧州のもう一つの翼:「FCAS」との競合・協力は?
ヨーロッパでは、GCAP(日英伊)とは別に、ドイツ、フランス、スペインが中心となり、もう一つの次世代戦闘機計画「FCAS(Future Combat Air System:将来戦闘航空システム)」を進めています。こちらも有人機(NGF)と無人機、戦闘クラウドを組み合わせた第6世代システムを目指しており、GCAPとコンセプトは非常に似ています。
かつては英国(テンペスト計画)と独仏西(FCAS)の協力も模索されましたが、主導権争いや企業間の利害調整が難航し、結果的に欧州では二つの計画が並立する形となりました。両者は将来の戦闘機市場(特に輸出)において競合する可能性がありますが、一方で開発費の高騰などから、将来的に何らかの技術協力や棲み分け、あるいは統合といった可能性も議論されています。この2大プロジェクトの行方は、欧州全体の防衛産業の未来を左右します。
猛追する中国:J-20から第6世代へ
GCAP開発を後押しする大きな要因が、中国の急速な軍事力近代化です。既に第5世代ステルス戦闘機とされる「J-20」を多数配備し、さらに艦載機としても運用可能なステルス機「J-31(FC-31)」の開発も進めています。
さらに、中国も第6世代戦闘機の開発に着手していると見られています。AIや無人機技術への積極的な投資を見る限り、将来的にGCAPやNGADに匹敵する戦闘機システムを登場させる可能性は否定できません。日本が欧州と連携してGCAPを進めることは、中国にとって自国への対抗措置と映り、強い警戒感を持ってその動向を注視していると考えられます。
韓国の独自路線:「KF-21ボラメ」
隣国の韓国は、独自開発のKF-21「ボラメ」戦闘機の試験飛行を進めています。これはステルス性能を限定的にする代わりに、コストを抑えつつ高い基本性能とネットワーク能力を目指す「第4.5世代」戦闘機です。2020年代後半の実用化を目指し、積極的に輸出も模索しています(前回触れたサウジアラビアへの提案もその一環です)。GCAPとは異なるカテゴリーの戦闘機ですが、国際市場やアジア太平洋地域の航空戦力バランスにおいて、独自の存在感を示そうとしています。
中東の視線:イスラエルの複雑な計算
中東地域では、イスラエルがGCAPの動向、特にサウジアラビアの参加問題に神経をとがらせていると考えられます。共通の脅威であるイランへの対抗上、サウジアラビアとの関係改善には関心があるものの、伝統的に重視してきた自国の「質的な軍事的優位性(QME)」が、サウジへの最先端技術移転によって将来的に脅かされることへの潜在的な懸念も抱えています。GCAPをめぐる動きは、微妙な中東の軍事バランスにも影響を与えうるため、イスラエルは公式な反応を控えつつも、その行方を注視しているはずです。
FOIPパートナーたちの視線:地域の安定とGCAP
日本が重視する「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けて連携する国々、例えばオーストラリアやインド、ASEAN諸国なども、GCAPの動向に強い関心を寄せています。
なぜなら、GCAPによって日本の防衛力が向上することや、欧州の主要国であるイギリス・イタリアがインド太平洋地域への関与を深めることは、この地域の安全保障環境やパワーバランスに直接影響を与えるからです。特に、既存の安全保障協力の枠組み、例えば日米豪印の「Quad(クアッド)」や、米英豪の「AUKUS(オーカス)」などとの関連で、GCAPがどのような位置づけになり、地域の安定にどう貢献していくのか、各国の戦略的な観点から注目されています。これらの国々は、GCAPの進展が自国の安全保障や地域秩序に与える影響を慎重に見極めようとしているでしょう。
まとめ
GCAPは、アメリカのNGAD、欧州のFCASといった最先端の計画や、急速に技術力を高める中国、独自の道を歩む韓国など、世界の様々な国々の動きと複雑に絡み合いながら進んでいます。それは単なる技術開発競争ではなく、地政学的な思惑や産業政策、同盟関係の変化といった要素も織り交ざった、壮大な国際ゲームの一部とも言えます。このグローバルな競争と協力のダイナミズムの中で、GCAPがその野心的な目標を達成できるか、その道のりは決して容易ではありません。
さて、世界に広げた視点を、次回は再び日本国内に戻します。GCAP計画は、日本の航空宇宙産業にとってどのような意味を持つのか? かつての国産旅客機MRJ(スペースジェット)開発中止の経験は活かせるのか? そして、イタリアが関心を示すP-1哨戒機の話題にも触れながら、日本の防衛装備協力の未来について考えていきます。
第7話:GCAPから広がる協力の翼 ~日本の防衛産業と国際協力の未来~
画像出典:防衛省・自衛隊ウェブサイト(https://www.mod.go.jp/j/policy/defense/nextfighter/index.html)公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)
-

【特集:最前線・南シナ海 – 急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代】第2話:海を守る最前線 ~海上保安庁とフィリピン沿岸警備隊、長年の絆と奮闘~
-

【特集:最前線・南シナ海 – 急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代】第3話:陸海空で連携強化! ~自衛隊とフィリピン軍、共同訓練の拡大~
-

【特集:最前線・南シナ海 – 急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代】第1話:なぜ今フィリピン? ~南シナ海緊迫化と日比「戦略的パートナーシップ」深化の背景~
-

第7話:GCAPから広がる協力の翼 ~日本の防衛産業と国際協力の未来~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第6話:GCAPを取り巻く世界の視線 ~米・欧・中・韓… 各国の戦闘機開発競争~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第5話:緊迫!5月イタリア会談の行方 ~サウジアラビア参加は実現するのか? 最新動向~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第4話:日本のジレンマ ~なぜサウジアラビア参加に慎重なのか?~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第3話:「仲間に入れてほしい」? サウジアラビアの接近 ~GCAPを揺るがすオイルマネーと地政学~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第2話:なぜアメリカではなかったのか? ~F-2後継機、日英伊協力へ至る道~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第1話:始動!日英伊共同開発「GCAP(ジーキャップ)」とは何か? ~未来の翼 、未来への選択~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】