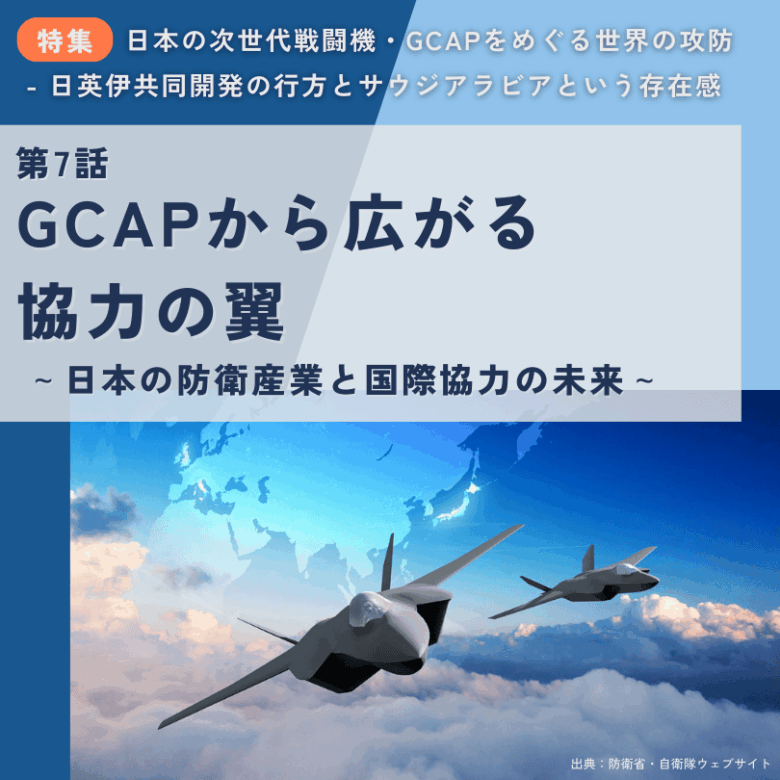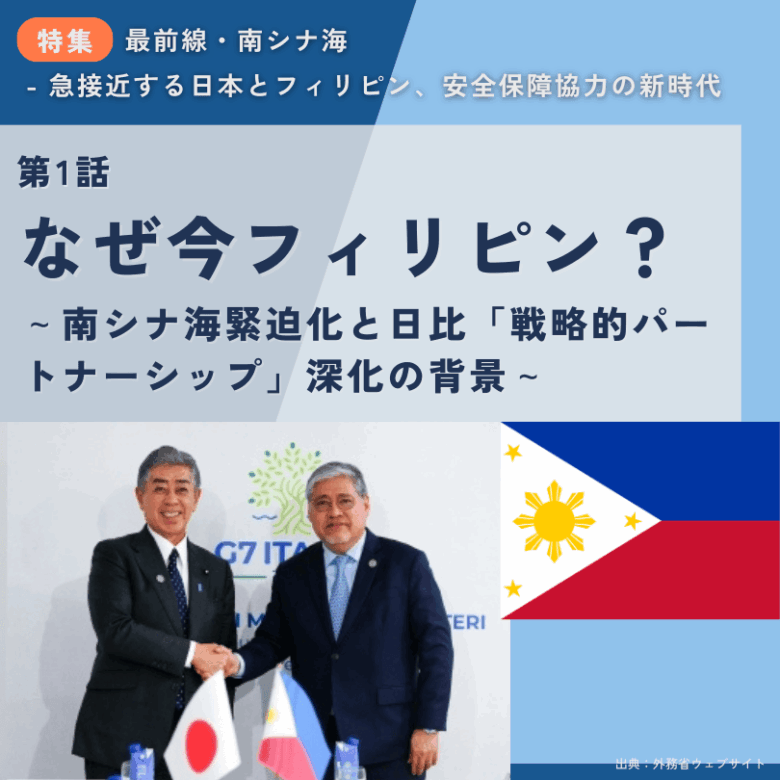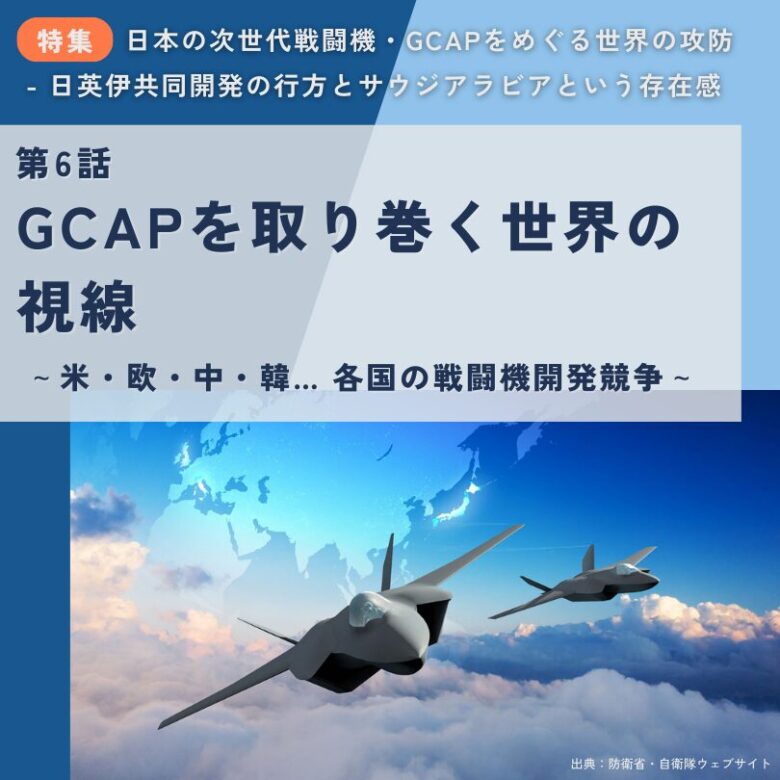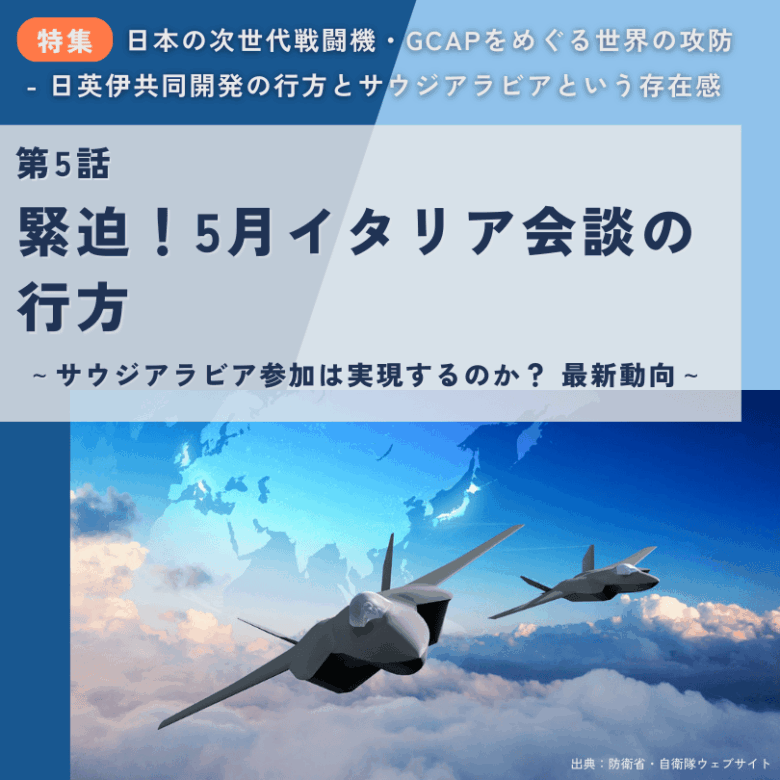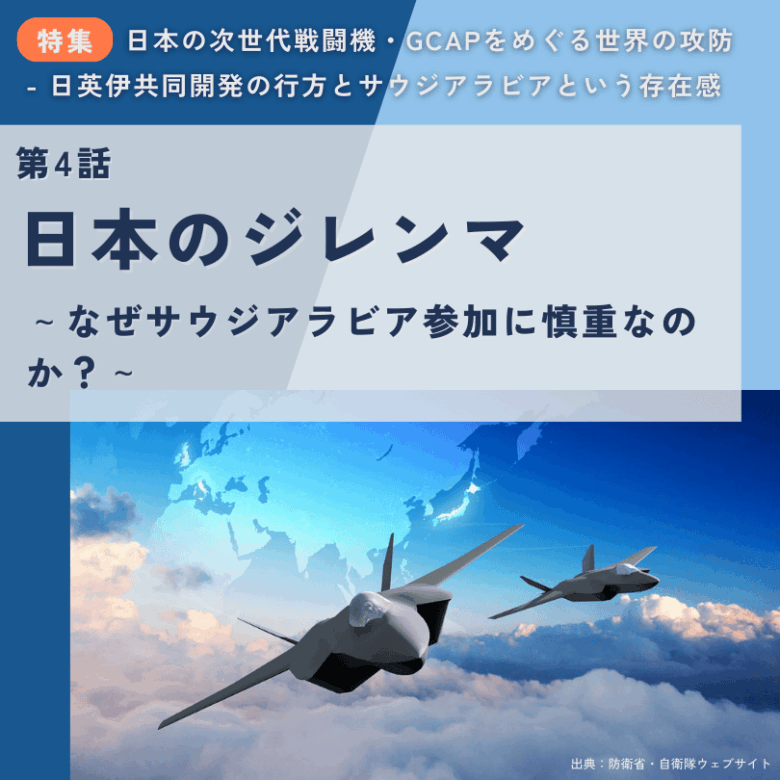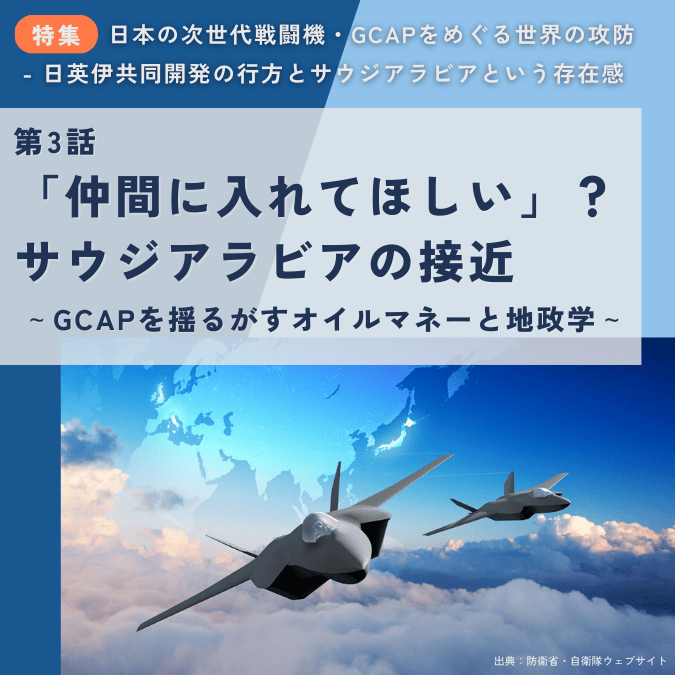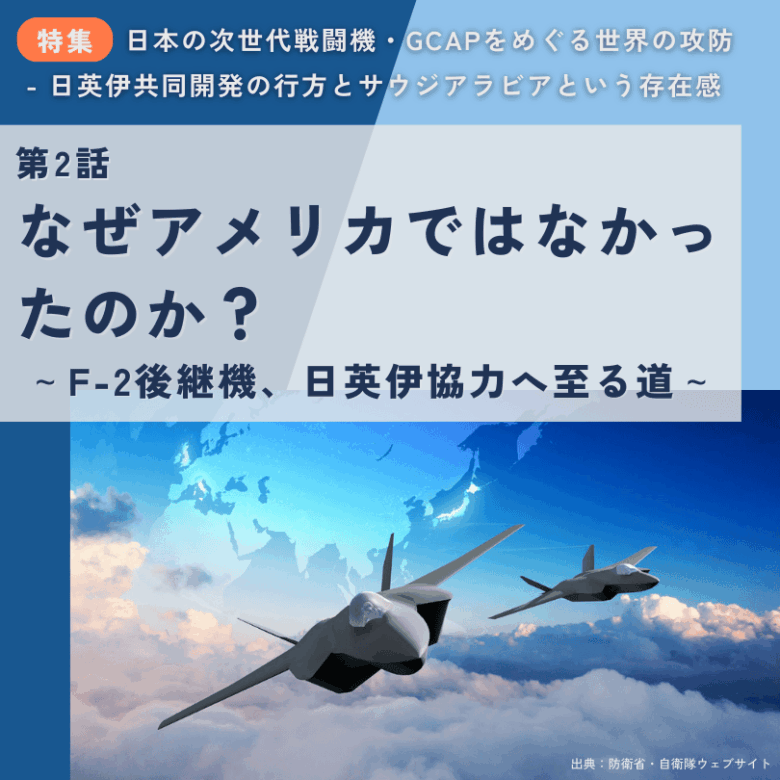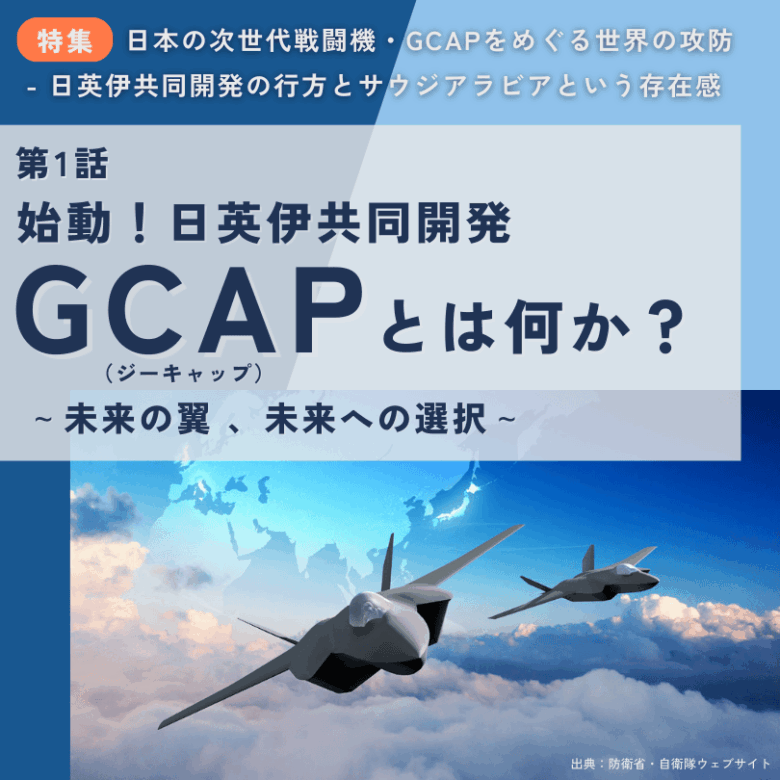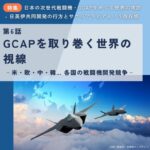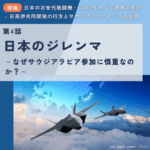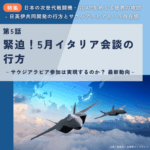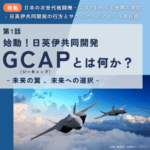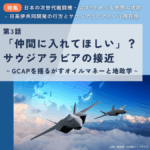第6話を読む
GCAPを取り巻く世界の視線 ~米・欧・中・韓… 各国の戦闘機開発競争~
【特集】
日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防
– 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感
第7話:GCAPから広がる協力の翼
~日本の防衛産業と国際協力の未来~

前回は、GCAP(次世代戦闘機共同開発計画)を取り巻く世界の国々の動きや、激化する次世代戦闘機開発競争の状況について解説しました。アメリカのNGAD、欧州のFCAS、そして中国や韓国など、様々なプレイヤーが存在する中で、GCAPが成功を収めるためには多くの課題を乗り越える必要があります。
さて、特集の最終回となる今回は、GCAPが日本国内にもたらす影響と、このプロジェクトを起点として広がりつつある国際協力の新たな動き、そして日本の防衛産業が抱える課題と未来について考えていきます。
GCAPが生む新たな協力? イタリアが日本の「P-1哨戒機」に関心
GCAPにおける日本、イギリス、イタリアの協力関係は、戦闘機開発だけに留まらない可能性を示唆する動きが出てきています。その代表例が、イタリアによる日本の「P-1哨戒機」導入検討のニュースです。

P-1は、日本の川崎重工業が開発・製造し、海上自衛隊が運用する純国産のジェット哨戒機です。高い対潜水艦・対水上艦艇探知能力を誇ります。イタリアは現在、旧式化した哨戒機の後継を探しており、今年(2025年)3月にはイタリア空軍トップがP-1を「可能性のあるオプションの一つ」と公式に言及しました。
この背景には、GCAPを通じて深まった日英伊の信頼関係や、日本の技術力への評価があると考えられます。もしイタリアがP-1の導入を決定すれば、日本の完成品の大型航空機としては初の海外輸出となり、日本の防衛装備移転政策にとって画期的な出来事となります。GCAPという中核プロジェクトが、他の分野での防衛協力をも促進する「触媒」となっている可能性を示しています。
日本の技術と産業を守る:GCAPが航空宇宙産業にもたらすもの
GCAPは、日本の安全保障に不可欠であると同時に、日本の航空宇宙産業全体にとっても極めて重要なプロジェクトです。
戦闘機の開発・製造には、機体構造、高性能エンジン、最先端のレーダーやセンサー、ソフトウェアなど、非常に幅広い分野における高度な技術力が結集されます。GCAPに日本が主体的に関与することで、これらの技術を国内で維持・発展させ、将来にわたって日本の技術的優位性を確保することにつながります。
また、戦闘機開発は、素材メーカーから部品メーカー、組み立てメーカーに至るまで、非常に多くの企業が関わる巨大な「すそ野」を持つ産業です。GCAPは、これらの関連企業の事業を支え、高度な技術を持つ人材を育成・確保し、日本の製造業全体の競争力維持にも貢献することが期待されています。
過去の教訓は活かせるか? 国産旅客機「MRJ」の挫折とGCAP
しかし、航空機の独自開発、特に最先端の機体を開発する道のりは平坦ではありません。日本の航空宇宙産業にとって、忘れてはならない経験が、国産初のジェット旅客機を目指した「MRJ(三菱リージョナルジェット、後にスペースジェットに改名)」プロジェクトの開発中止です。
MRJは、技術的な問題や、航空機が安全基準を満たしていることを証明する「型式証明」取得の難航、度重なる納入延期と開発費の高騰など、多くの困難に直面し、最終的に市場投入を断念せざるを得ませんでした。
この経験から得られた教訓、例えば、
- 複雑な国際基準(特に型式証明)への対応能力
- 大規模プロジェクトにおける厳格なコスト管理とスケジュール管理
- サプライチェーン・マネジメントの重要性
- リスクを見据えたプロジェクトマネジメント能力
などは、GCAPプロジェクトを成功させる上でも不可欠です。GCAPは国際共同開発であり、MRJとは異なる側面も多いですが、過去の失敗を真摯に分析し、その教訓を活かしていくことが強く求められています。
GCAPの輸出は? 日本の防衛装備移転のこれから
GCAPで開発される戦闘機は、日英伊3カ国での使用が前提ですが、将来的には他の友好国への輸出も視野に入れられていると言われています。輸出が実現すれば、開発・生産コストをさらに低減できるだけでなく、日本の国際的な影響力向上にも繋がります。
しかし、そのためにはいくつかのハードルがあります。前回触れた「防衛装備移転三原則」の運用をどうするか、という国内での議論。そして、アメリカのNGADや欧州のFCASなど、強力なライバルがひしめく国際市場で、GCAPが競争力を持ち、輸出先を獲得できるかという問題です。輸出を念頭に置くならば、開発段階から輸出相手国のニーズもある程度考慮する必要が出てくるかもしれません。サウジアラビアの参加問題も、この輸出戦略と無関係ではありません。
GCAPは、日本の防衛装備移転政策が新たな段階へ進むための、試金石となる可能性も秘めているのです。
まとめと今後の展望
日英伊共同開発プロジェクト「GCAP」。それは、日本の空を守る未来の翼であると同時に、国際協力の新しいモデルであり、日本の技術と産業の将来を左右する可能性を秘めた、多面的な挑戦です。
本特集では、GCAPの概要から、その誕生の背景、最大の懸案であるサウジアラビア参加問題、そしてGCAPを取り巻く世界の国々の動きや、日本国内への影響まで、様々な角度から解説してきました。
今後注目すべきは、
- 5月に予定される(あるいは調整中の)日英伊(+サウジ?)防衛相会談の結果と、サウジアラビア参加問題の行方。
- 開発スケジュールの遵守と、具体的な技術開発の進捗。
- GCAPと米NGAD、欧州FCASとの関係性の変化。
- 変化する国際情勢(ウクライナ、中東、東アジアなど)がGCAP計画に与える影響。
- 日本の防衛装備移転政策に関する議論の進展。
これらの動きは、GCAPの未来、そして日本の安全保障と国際的な立ち位置に大きな影響を与えます。本メディアでは、今後もGCAPに関する最新情報を注視し、分析・解説を続けていきたいと思います。「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた日本の取り組みという大きな文脈の中でも、このGCAPの動向は重要な意味を持ち続けるでしょう。
(特集・了)
画像出典:防衛省・自衛隊ウェブサイト(https://www.mod.go.jp/j/policy/defense/nextfighter/index.html)公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)
-

【特集:最前線・南シナ海 – 急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代】第2話:海を守る最前線 ~海上保安庁とフィリピン沿岸警備隊、長年の絆と奮闘~
-

【特集:最前線・南シナ海 – 急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代】第3話:陸海空で連携強化! ~自衛隊とフィリピン軍、共同訓練の拡大~
-

【特集:最前線・南シナ海 – 急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代】第1話:なぜ今フィリピン? ~南シナ海緊迫化と日比「戦略的パートナーシップ」深化の背景~
-

第7話:GCAPから広がる協力の翼 ~日本の防衛産業と国際協力の未来~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第6話:GCAPを取り巻く世界の視線 ~米・欧・中・韓… 各国の戦闘機開発競争~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第5話:緊迫!5月イタリア会談の行方 ~サウジアラビア参加は実現するのか? 最新動向~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第4話:日本のジレンマ ~なぜサウジアラビア参加に慎重なのか?~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第3話:「仲間に入れてほしい」? サウジアラビアの接近 ~GCAPを揺るがすオイルマネーと地政学~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第2話:なぜアメリカではなかったのか? ~F-2後継機、日英伊協力へ至る道~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】
-

第1話:始動!日英伊共同開発「GCAP(ジーキャップ)」とは何か? ~未来の翼 、未来への選択~【特集・日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防 – 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感】