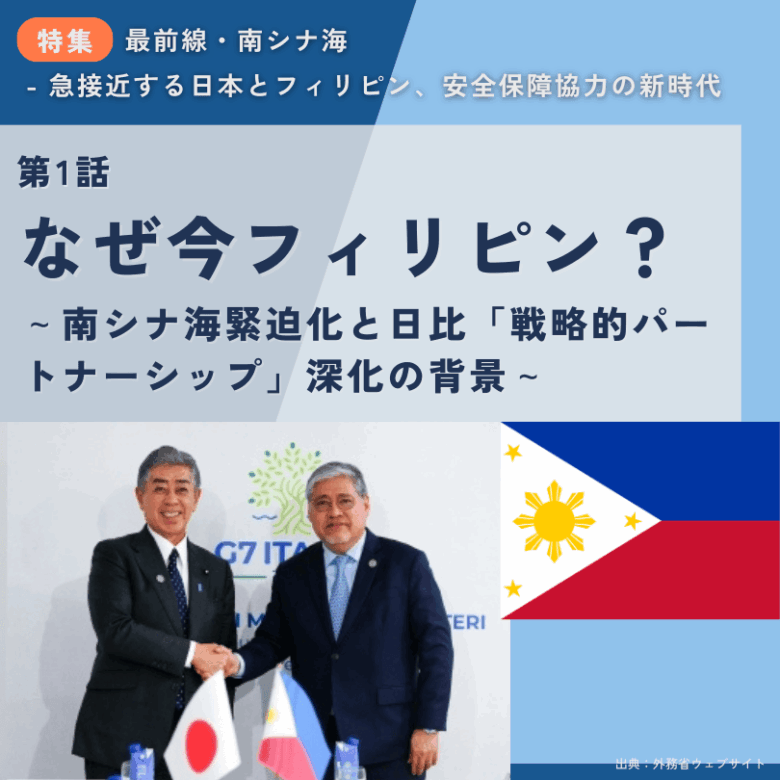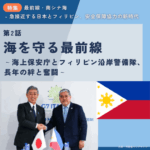【特集】
最前線・南シナ海
-急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代
第1話:なぜ今フィリピン?
~南シナ海緊迫化と日比「戦略的パートナーシップ」深化の背景~

連日のようにニュースで報じられる、南シナ海をめぐる緊張の高まり。つい最近も、フィリピンの巡視船が中国海警局の船から危険な妨害行為を受けた、と伝えられました。係争海域でのこのような威圧的な行動は、残念ながら後を絶ちません。
一方で、アメリカとフィリピンは空軍合同演習「コープ・サンダー」を行い、米国防長官がフィリピンに新型兵器を配備すると発表、さらにF-16戦闘機の売却計画も進んでいるとされます。これに反発するように、中国が南シナ海に爆撃機を展開させるなど、米中間の対立も先鋭化しています。
こうした激動の渦中で、日本とフィリピンの関係が、かつてないスピードで深まっていることにお気づきでしょうか? 両国関係は「戦略的パートナーシップ」へと格上げされ、安全保障面での協力が急速に進んでいます。
なぜ今、日本はフィリピンとの関係強化をこれほどまでに重視するのでしょうか? 本特集では、その背景にある地政学的な現実と、関係国の思惑を解き明かしていきます。第1回は、すべての始まりである「なぜ今、フィリピンなのか?」その理由から探っていきましょう。
南シナ海で何が起きているのか? フィリピンが直面する現実
フィリピンが直面する最大の課題は、南シナ海における中国の急速な海洋進出です。中国は、南シナ海のほぼ全域に赤い線で囲った独自の権利(通称「九段線」)を主張しています。しかし、この主張には国際法上の根拠がない、というのが2016年に示された国際的な司法判断(仲裁裁判所判決)です。
にもかかわらず、中国はこの判断を無視し、南シナ海の岩礁を埋め立てて人工島を造成、滑走路やレーダー施設などを建設し、軍事拠点化を進めてきました。さらに近年は、中国海警局の大型船や「海上民兵」と呼ばれる多数の漁船を使って、フィリピンの漁船や公船(巡視船など)の活動を妨害する行為を繰り返しています。
放水銃の使用、レーザー照射、進路妨害、そして冒頭で触れたような危険な接近や衝突未遂…。これらは、力によって現状を変えようとする威圧的な行動であり、フィリピンの主権や、魚を獲ったり資源を探したりする権利(海洋権益)を脅かす、非常に深刻な問題となっています。
フィリピンの決断:中国への「ノー」と日米連携強化
このような中国の強硬な姿勢に対し、2022年に就任したフィリピンのマルコス大統領は、前政権の方針を大きく転換しました。経済的な結びつきを重視して中国との対話を優先したドゥテルテ前大統領とは異なり、マルコス大統領は中国の威圧的な行動に対しては国際社会に訴え、断固として「ノー」の姿勢を示しています。
そして、自国の主権と権益を守るために、伝統的な同盟国であるアメリカとの関係を再強化し、同時に日本との連携を急速に深める道を選びました。法の支配や航行の自由といった国際的なルールを守るためには、同じ価値観を持つ国々との協力が不可欠だ、という強い意志の表れと言えるでしょう。
日本にとってなぜフィリピンは重要なのか?
日本がフィリピンとの関係強化を急ぐのには、明確な理由があります。
- 海の生命線「シーレーン」
-
日本が中東などから輸入する原油や、様々な物資の多くは、南シナ海を通って運ばれてきます。この海の道(シーレーン)の安全確保は、日本の経済活動や私たちの暮らしにとって死活的に重要であり、フィリピンはそのすぐ隣に位置する重要な国です。
- 「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現
-
日本が提唱するFOIP構想は、力による一方的な現状変更を許さず、法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序を守ることを目指しています。南シナ海で起きていることは、まさにこの秩序への挑戦であり、フィリピンと協力してこの問題に対処することは、FOIPを実現する上で鍵となります。
- 地域の安定と日本の安全保障
-
地理的にも近いフィリピンの安定は、東アジア全体の安定に繋がります。また、中国の海洋進出は日本にとっても他人事ではなく、フィリピンと連携して地域全体の抑止力を高めることは、日本の安全保障にも資するのです。
こうしたことから、日本はフィリピンとの関係を単なる友好国から「戦略的パートナー」へと引き上げ、安全保障協力だけでなく、経済協力(道路や鉄道などのインフラ整備支援)や防災、人的交流など、あらゆる分野で関係を強化しようとしています。
再び存在感を増すアメリカ:米比同盟の再活性化
フィリピンの政策転換を受け、アメリカも同盟関係の再強化を急速に進めています。かつて1992年にフィリピンから米軍基地が完全撤退した歴史がありますが、現在の安全保障環境の変化を受け、再び連携を深める方向に大きく舵を切りました。
- 基地へのアクセス拡大
-
「EDCA(エドカ:防衛協力強化協定)」に基づき、米軍がフィリピン国内で使用できる拠点を増やし、共同訓練や災害救援、そして万一の場合の対応能力を高めています。
- 共同訓練の活発化
-
空軍の「コープ・サンダー」や、陸海空軍・海兵隊が参加する大規模演習「バリカタン」などを通じ、両軍の連携を強化しています。
- フィリピン軍の能力向上支援
-
最新ニュースにあるF-16戦闘機の売却計画や新型兵器の配備発表のように、フィリピン軍が自国を守る能力を高めるための支援も積極的に行っています。
この米比同盟の再活性化は、南シナ海における抑止力を高める上で非常に重要であり、日本の対フィリピン協力とも連携しながら進められています。
まとめ
南シナ海での中国による力による現状変更の試みが続く中、フィリピンは日米との連携を強化し、自国の主権と地域の安定を守ろうとしています。日本にとっても、フィリピンはシーレーン防衛やFOIP実現のための重要な戦略的パートナーです。日比、そして米比関係の深化は、インド太平洋地域の未来を考える上で、今最も注目すべき動きの一つと言えるでしょう。
では、具体的に日本はフィリピンとどのような安全保障協力を進めているのでしょうか?
次回は、その最たる例とも言える、日本の海上保安庁によるフィリピン沿岸警備隊への支援に焦点を当て、その長年の取り組みと、南シナ海の最前線で果たしている役割について詳しく見ていきます。
画像出典:外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sea2/ph/pageit_000001_01294.html)
公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)