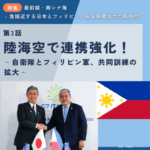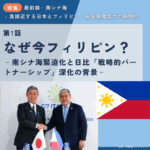第1話を読む
なぜ今フィリピン? ~南シナ海緊迫化と日比「戦略的パートナーシップ」深化の背景~
【特集】
最前線・南シナ海
-急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代
第2話:海を守る最前線
~海上保安庁とフィリピン沿岸警備隊、長年の絆と奮闘~

前回は、南シナ海での緊張が高まる中、日本とフィリピンの関係が「戦略的パートナーシップ」へと深化している背景について解説しました。今回は、その日比協力の中でも特に長い歴史を持ち、今まさに最前線で重要な役割を果たしている「海上保安分野」での協力に焦点を当てます。日本の海上保安庁(JCG)とフィリピン沿岸警備隊(PCG)の間に築かれてきた強い絆と、それが南シナ海の平和と安定にどう貢献しているのかを見ていきましょう。
なぜ日本はフィリピンの「海の警察」を支援するのか?
7,000以上の島々から成り、世界第5位の長さを誇る海岸線を持つフィリピンにとって、海上交通は経済・社会の生命線です。しかし近年、島々を結ぶ船の交通量増加や老朽化、そして相次ぐ自然災害により、海難事故のリスクが高まっています(JICAの2013年資料によると、当時の海難事故発生件数は過去5年平均で以前の約2倍に増加)。さらに、人やモノの移動活発化に伴い、密輸、密漁、テロといった海上犯罪への対処も喫緊の課題となっています。
こうしたフィリピンの「海の安全」を守る役割を担うのが、フィリピン沿岸警備隊(PCG)です。しかし、広大な海域に対して、PCGが保有する船の数は十分とは言えず、海難救助や法執行活動を迅速かつ広範囲に行うための能力向上が長年の課題でした。
日本の海上保安庁は、こうしたフィリピンの状況を踏まえ、長年にわたりPCGへの支援を継続してきました。その背景には、
- 日本のシーレーン(海上交通路)の安全確保に繋がること。
- 国際法に基づく自由で開かれた海洋秩序」の維持・強化に貢献すること(これは日本のFOIP戦略の柱でもあります)。
- ODA(政府開発援助)などを通じた支援が、両国間の友好と信頼関係を深めること。
といった、日本の国益にも深く関わる理由があります。
海を守る船をフィリピンへ:巡視船供与と日本の技術
日本の支援の大きな柱が、巡視船の供与です。
日本は2013年以降、円借款による「海上安全対応能力強化事業」を通じて、日本の巡視船(海上保安庁の「びざん型」などがベースとなっています)の技術を活かした40メートル級の多目的応答船(MRRV)を10隻フィリピンに供与しました。これらはフィリピンでは一般的に「パロラ」級と呼ばれており、ネームシップの「BRP Tubbataha」をはじめとする同級船が、PCGの主力として南シナ海での監視活動や、国内での海上犯罪取締り、海難救助、災害対応などに幅広く活躍しています。
さらに、より大型(97メートル級)で沖合での活動能力が高い巡視船「テレサ・マグバヌア」級も2隻供与。そして2023年には、新たに5隻の大型巡視船の供与も表明されるなど、日本の支援は継続的に強化されています。
ハードだけじゃない:「人づくり」と「維持管理」への視点
日本の支援は、船という「ハード」の供与だけにとどまりません。過去の類似の支援事業の教訓(インドネシアへの防災船供与など)も踏まえ、供与した船を有効に活用し、長く使い続けるための「ソフト」面、すなわち「人づくり(能力構築支援)」と「維持管理体制」の強化にも注力しています。
- 人材育成
-
海上保安庁は、PCG職員に対し、操船・整備技術、法執行(捜索救助、海上犯罪取締り、環境保護など)、国際航空法、艦船整備など、多岐にわたる分野で研修や訓練を実施してきました(過去には「海上保安人材育成プロジェクト」などの技術協力も行われています)。
- 維持管理支援
-
船を安全に長く運用するためには、適切なメンテナンスが不可欠です。交換部品の安定供給や、計画的な保守・点検に関するノウハウの共有なども、支援の重要な要素となっています。
こうした包括的な支援により、PCG全体の組織能力向上を目指しています。
最前線での奮闘と国際協力の輪
日本の支援によって能力を高めたフィリピン沿岸警備隊(PCG)は今、南シナ海の最前線で、日々中国海警局などによる威圧的な行動に直面しながらも、粘り強く任務を遂行しています。日本から供与された巡視船が、国際法に基づき冷静に対応しつつ、フィリピンの主権と権益を守る姿は、国際社会にも広く報じられています。
日本だけでなく、アメリカやオーストラリアも訓練支援や中古船の供与などを継続的に行っており、フランスも過去には船舶供与を検討していた時期がありました(JICA 2013年資料より)。また、ベトナムや韓国、インドネシアなど、他のASEAN諸国等とも連携を進めています。
まとめ
日本の海上保安庁によるフィリピン沿岸警備隊への支援は、巡視船という「モノ」の提供に加え、長年の「人づくり」や運用ノウハウの共有を含む、息の長い取り組みです。それは、フィリピンの海上安全能力向上に貢献するだけでなく、南シナ海の平和と安定、そしてルールに基づく国際秩序を守るための、日本の「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」戦略を具体化する重要な柱となっています。
しかし、日々エスカレートする可能性のある現場の状況に対し、海上保安機関だけでの対応には限界もあります。より高度な抑止力や対処能力が求められる中、日比協力は次の段階、すなわち軍同士の連携強化へと進んでいきます。
次回は、近年急速に活発化している自衛隊とフィリピン軍の共同訓練に焦点を当て、陸海空それぞれの分野で、どのように連携が深化しているのかを見ていきます。
【参考文献】
- JICA「フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事業 事業事前評価表」(2013年12月)https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2013_PH-P257_1_s.pdf