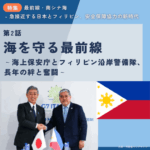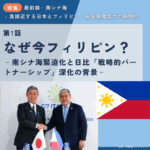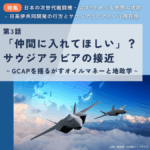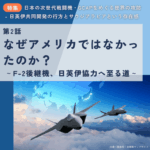第2話を読む
海を守る最前線 ~海上保安庁とフィリピン沿岸警備隊、長年の絆と奮闘~
【特集】
最前線・南シナ海
-急接近する日本とフィリピン、安全保障協力の新時代
第3話:陸海空で連携強化!
~自衛隊とフィリピン軍、共同訓練の拡大~

前回は、日本の海上保安庁とフィリピン沿岸警備隊が、巡視船の供与や人材育成を通じて、南シナ海の最前線で「海の安全」を守るために長年協力してきた姿を見ました。しかし、地域の安全保障環境が厳しさを増す中、日比間の協力は海上保安機関レベルに留まらず、自衛隊とフィリピン国軍との連携へと、急速にその裾野を広げ、深化させています。今回は、その最たる例である共同訓練の活発化や、今後の協力の枠組みについて見ていきましょう。
陸・海・空で活発化・多角化する共同訓練
近年、自衛隊とフィリピン軍は、二国間またはアメリカやオーストラリアなども交えた多国間の枠組みで、共同訓練の回数と内容を飛躍的に向上させています。これは、両国の部隊が実際に顔を合わせ、共に汗を流すことで、相互理解を深め、いざという時に連携して行動できる能力(相互運用性)を高めることを目的としています。
- 航空自衛隊とフィリピン空軍
-
災害の多い両国にとって重要な人道支援・災害救援(HA/DR)分野での協力は継続的に行われています。航空自衛隊はフィリピン空軍に対し、専門知識の共有や共同での図上演習などを通じて能力構築支援を実施し、災害対応能力の向上に貢献しています。また、航空医学分野でのセミナー開催といった専門分野での協力も進められています。ハイレベルでの交流も活発で、日本の航空幕僚長がフィリピンを訪問したり、フィリピン空軍主催のシンポジウムに参加したりといった機会も設けられています。戦闘機部隊の交流としては、特筆すべき出来事として、2022年12月に航空自衛隊のF-15戦闘機がフィリピンのクラーク空軍基地へ初めて寄港し、フィリピン空軍との間で親善訓練を行いました。さらに、日米豪などが参加する多国間演習「コープ・ノース・グアム」にフィリピン空軍が参加するなど、多国間の枠組みでの連携も深まっています。
- 海上自衛隊とフィリピン海軍
-
海上自衛隊とフィリピン海軍も、南シナ海を含むフィリピン近海で二国間共同訓練を定期的に実施しています。2019年6月には護衛艦「いずも」や「むらさめ」がフィリピン海軍のフリゲートと訓練を行うなど、戦術技量の向上や人道支援・災害救援(HA/DR)、海賊対処などを想定した連携が重ねられています。加えて、アメリカ海軍なども交えた多国間の枠組みでの協力も活発です。日米比が共同で参加する「サマサマ(SAMASAMA)」や「カガンダン(KAGANDAHAN)」といった訓練が2023年10月にも実施されたほか、世界最大規模の海上演習である環太平洋合同演習「RIMPAC(リムパック)」にも両国は参加し、連携を深めています。
- 陸上自衛隊とフィリピン陸軍・海兵隊
-
陸上自衛隊とフィリピン陸軍・海兵隊との間でも協力は進んでいます。特に人道支援・災害救援(HA/DR)分野での連携が行われているほか、多国間の枠組みも重要です。アメリカ軍とフィリピン軍が主体となって毎年実施する大規模演習「バリカタン」には、陸上自衛隊が近年、当初のオブザーバー参加から実動部隊としての参加へと、その関与を深めています。こうした多国間での連携を通じて、陸上部隊間の相互運用性の向上も図られています。
これらの訓練は、単に技術を磨くだけでなく、両国の強い意志の表れでもあります。それは、2022年に開催された初の外務・防衛閣僚会合(2+2)の共同声明で確認された、「ルールに基づく国際秩序への挑戦に対応するため、安全保障・防衛協力を強化する」という目標に沿ったものです。
よりスムーズな連携へ:「円滑化協定(RAA)」交渉開始
共同訓練や部隊間の相互訪問をさらに活発化・円滑化させるため、日本とフィリピンは「円滑化協定(RAA: Reciprocal Access Agreement)」の締結に向けた交渉を開始することで合意しました。
RAAは、自衛隊が相手国を訪問したり、相手国の軍隊が日本を訪問したりする際の入国手続きや滞在中の法的地位、武器・弾薬の持ち込み手続きなどを簡素化し、共同活動をスムーズに行うための重要な法的基盤です。これが締結されれば、より実践的で大規模な共同訓練や、災害発生時の迅速な相互支援などが可能になると期待されます。日本にとっては、オーストラリア、イギリスに次ぐ3例目(東南アジア諸国とは初)のRAA締結を目指すことになります。この交渉開始は、これまでの日比防衛相会談などを通じたハイレベルでの継続的な協議の成果と言えます。
装備協力も新たな段階へ:レーダー輸出からOSA活用まで
防衛装備分野での協力も着実に進展しています。日本の完成品の防衛装備としては初の輸出案件となった、フィリピン空軍向けの警戒管制レーダー(三菱電機製)4基の移転が進められています。これは、フィリピンの広大な領域を監視する能力を大きく向上させるもので、日比2+2共同声明などでもその進展が歓迎されています。
それ以前にも、海上自衛隊の練習機TC-90(5機)や陸上自衛隊のヘリコプターUH-1Hの部品などがフィリピンへ移転され、人材育成や機体の維持整備に貢献してきました。
さらに、日本が2023年に開始した新たな支援の枠組み「政府安全保障能力強化支援(OSA)」の最初の適用対象国の一つにフィリピンが選ばれました。これにより、フィリピンのニーズに基づき、沿岸監視レーダーなどの供与が進められる予定です。OSAは、軍などに対する安全保障目的での直接的な支援を可能にするもので、今後の日比装備協力の可能性を広げるものと期待されています。
これらの装備協力は、日比防衛相会談や防衛当局間協議(MM協議)などを通じて、両国間で緊密に協議・推進されています。
なぜ協力はここまで深化するのか?
日比間の防衛協力がこれほど急速に深化・拡大している背景には、
- 南シナ海をめぐる共通の安全保障上の懸念。
- 日米比、さらには日米豪比といった多国間の連携強化の流れ。
- 日本自身の、より積極的な国際貢献と地域の平和と安定へのコミットメント。
- フィリピン側の防衛力近代化への強い意欲と、長年の協力で培われた日本への信頼。
- ハイレベルでの緊密な対話(首脳会談、2+2、防衛相会談、実務者協議など)の継続。
といった要因が複合的に作用していると言えるでしょう。特に、法の支配や航行の自由といった価値観を共有する「戦略的パートナー」として、共に地域の課題に取り組むという強い意志が両国間に存在します。
まとめ
自衛隊とフィリピン軍の共同訓練は、陸海空すべての分野で、二国間・多国間の両面で活発化し、より実践的なレベルへと進化しています。RAA交渉の開始やOSAによる支援は、その協力関係をさらに深化させるための重要なステップです。これは、日比関係が新たな段階に入ったことを明確に示しています。
しかし、協力が深化する一方で、それを実質的な抑止力や対処能力の向上にどう繋げていくか、また、政権交代などの影響を受けずに協力関係をいかに持続させていくか、といった課題も残されています。
そして、この日比協力の動きは、地域全体の安全保障の構図、特にアメリカを含めた「日米比」の連携という文脈の中で、さらに大きな意味を持ってきます。
次回は、この日米比3カ国の安全保障協力がどのように進展し、南シナ海、ひいてはインド太平洋地域全体の未来にどのような影響を与えようとしているのか、詳しく見ていきます
第4話は近日公開予定です、お待ち下さい。
参考文献・出典
◆ハイレベル協議・合意関連
- 外務省:岸田総理大臣のフィリピン共和国訪問(2023年11月3日)(RAA交渉開始合意など) https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sea2/ph/page4_006040.html
- 防衛省:第1回日・フィリピン外務・防衛閣僚会合(「2+2」)共同声明(仮訳)(2022年4月9日) https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/area/2022/20220409_phl-j_a.html
- 防衛省:第1回日・フィリピン外務・防衛閣僚会合(「2+2」)開催概要(2022年4月9日) https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/area/2022/20220409_phl-j_b.html
- 防衛省:日比防衛相会談 関連発表
- 防衛省:日フィリピン防衛当局間(MM)協議の開催(結果)(2022年10月24日) https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/area/2022/20221024_phl-j.html
◆航空自衛隊とフィリピン空軍の協力関連
- 航空自衛隊 活動報告:日比人道支援・災害救援(HA/DR)共同訓練・能力構築支援
- 航空自衛隊 活動報告:フィリピンに対する航空医学分野の能力構築支援について https://www.mod.go.jp/asdf/report/post/000522.html
- 航空自衛隊 活動報告:航空幕僚長のフィリピン関連活動
- フィリピン・ベトナム出張(2023年11月):https://www.mod.go.jp/asdf/report/post/000566.html
- 比空軍主催シンポジウム参加(2022年7月):https://www.mod.go.jp/asdf/report/post/000493.html
- 航空自衛隊 報道発表資料:フィリピン空軍副司令官の来日について(2023年10月13日) https://www.mod.go.jp/asdf/report/uploads/docs/20231013.pdf
- 航空自衛隊 報道発表資料:日比幕僚協議の実施について(2024年6月7日) https://www.mod.go.jp/asdf/report/uploads/docs/20240607j.pdf
- 航空自衛隊 報道発表資料:フィリピン空軍防空コマンド司令官による空幕長表敬について(2025年3月12日) https://www.mod.go.jp/asdf/report/uploads/docs/20250312.pdf
- 在フィリピン日本国大使館:F-15戦闘機のクラーク訪問(2022年12月) https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01050.html
◆海上自衛隊とフィリピン海軍の協力関連
- 海上自衛隊 自衛艦隊ニュース:「日米豪加独新共同訓練(NOBLE STINGRAY)及び日米比共同訓練(Exercise SAMASAMA 2023)について」(2023年10月17日) https://www.mod.go.jp/msdf/sf/news/2023/10/1017_1.html
- 海上自衛隊 お知らせ:「護衛艦「いずも」及び「むらさめ」のフィリピン共和国訪問について」(2019年6月30日) https://www.mod.go.jp/msdf/release/201906/20190630.pdf
◆陸上自衛隊・統合幕僚監部とフィリピン軍の協力関連(バリカタンなど)
- 統合幕僚監部 報道発表資料:米比主催多国間共同訓練バリカタン25への参加について(2025年4月11日) https://www.mod.go.jp/js/pdf/2025/p20250411_02.pdf
- 統合幕僚監部 報道発表資料:米フィリピン共同演習(バリカタン12)への参加について(2012年3月8日) https://www.mod.go.jp/js/pdf/2012/p20120307.pdf
- (※その他、陸上自衛隊のHA/DR協力やバリカタン参加に関する報道発表ページなどがあれば追記)
◆多国間協力関連
- 防衛省:日米豪比防衛相会談について(2023年6月3日) https://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/2023/0603a_usa_aus_phl-j.html
- 防衛省:日米比防衛実務者協議の開催について(2022年9月15日) https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/area/2022/20220915_usa_phl-j.html
◆防衛装備・技術協力関連
- 防衛省 報道発表:フィリピンへの警戒管制レーダーの移転について
- 2023年11月2日発表:https://www.mod.go.jp/j/press/news/2023/11/02d.html
- 2022年10月3日発表:https://www.mod.go.jp/j/press/news/2022/10/03a.html
- 外務省:政府安全保障能力強化支援(OSA:Official Security Assistance) https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/ipc/page4_005828.html
- (※TC-90、UH-1H部品移転に関する過去の報道発表などがあれば追記)
◆ODA・その他
- JICA:フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事業 事業事前評価表(2013年12月) https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2013_PH-P257_1_s.pdf