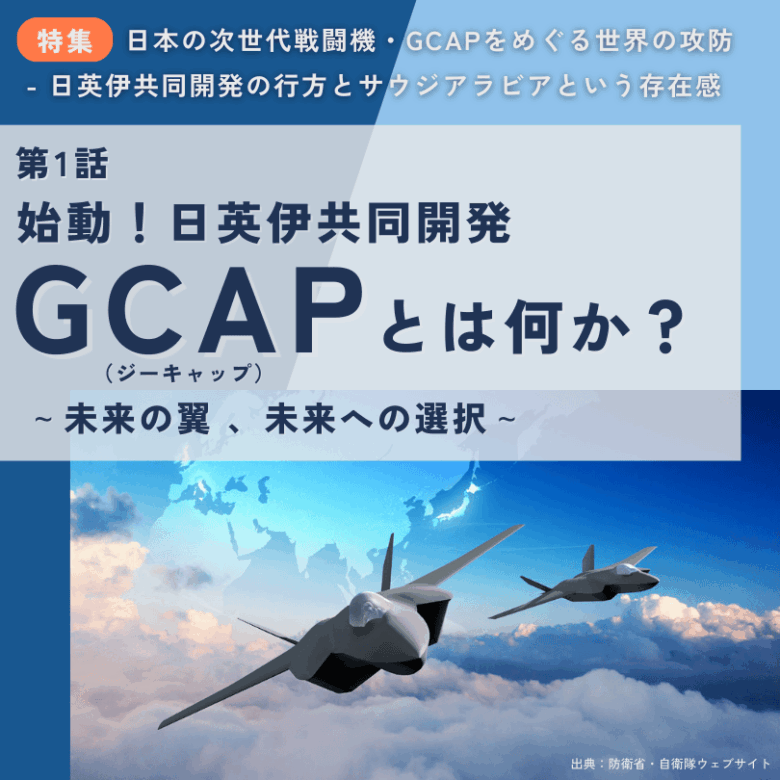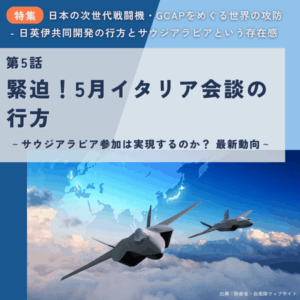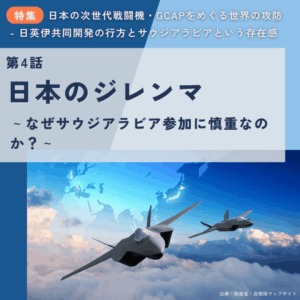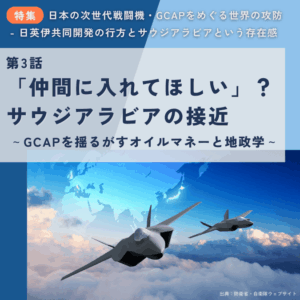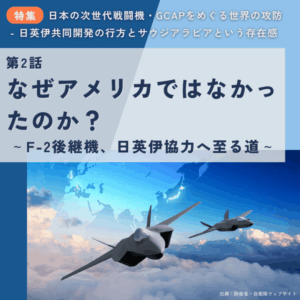【特集】
日本の次世代戦闘機・GCAPをめぐる世界の攻防
– 日英伊共同開発の行方とサウジアラビアという存在感
第1話:始動!日英伊共同開発「GCAP(ジーキャップ)」とは何か?
~未来の翼 、未来への選択~

日本の空を守り続けてきた航空自衛隊の「F-2支援戦闘機」。その引退が視野に入る中、後継となる次期戦闘機の開発計画が今、大きな注目を集めています。その名は「GCAP(ジーキャップ:Global Combat Air Programme / グローバル戦闘航空プログラム)」。
これは、日本がイギリス、イタリアというヨーロッパの国々と手を組み、未来の航空戦闘を見据えた全く新しい戦闘機、いわゆる「第6世代戦闘機」を共同で開発・配備しようという、壮大な国際プロジェクトです。
単に新しい飛行機を作るという話ではありません。厳しさを増す国際情勢の中で、日本が自国の平和と安全を守り抜くために下した重要な決断であり、法の支配や自由貿易といった価値観を共有する国々と連携して「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」を実現していく上でも、大きな意味を持つ動きと言えるでしょう。
本特集では、このGCAP計画の全貌と、その行方を左右するサウジアラビアの存在感、そして計画を取り巻く世界の動きを追っていく。第1回となる今回は、まず「GCAPとは何か?」その基本的なところから、目指している未来の戦闘機像までを、分かりやすく解説します。
GCAP計画のキホン:誰が、何を、いつまでに?
まずはGCAP計画の基本的な情報を押さえておきましょう。
- 正式名称
-
Global Combat Air Programme(グローバル戦闘航空プログラム)
- 参加国
-
日本、イギリス、イタリア の3カ国
- 目的
-
現在使われている戦闘機の後継機となる、次世代の高性能戦闘機を共同で開発し、配備すること。
日本:「F-2支援戦闘機」の後継機
イギリス・イタリア:「ユーロファイター・タイフーン」戦闘機の後継機 - 目標時期
-
2035年頃までに最初の機体を配備することを目指しています。
なぜ今、新しい戦闘機が必要なのか?
そもそも、なぜ莫大な費用と時間をかけてまで、新しい戦闘機を開発する必要があるのでしょうか? それには、主に二つの理由があります。
一つは、日本の周辺を取り巻く安全保障環境の変化です。近年、近隣諸国では軍事力の近代化が急速に進んでおり、高性能な戦闘機の開発や配備も進んでいます。将来、日本の平和と安全を脅かすような事態が発生した際に、現在の戦闘機だけでは十分に対応できなくなる可能性が指摘されています。
もう一つは、航空戦闘のあり方を変える技術の進歩です。レーダーに映りにくい「ステルス技術」はもちろん、戦闘機同士や地上部隊が瞬時に情報を共有する「ネットワーク技術」、パイロットを助ける「AI(人工知能)」、そしてパイロットが乗らない「無人機(ドローン)」との連携など、新しい技術が次々と登場しています。将来の空の戦いで優位に立つためには、これらの最新技術を積極的に取り込んだ戦闘機が必要不可欠になっているのです。
目指すは「第6世代」! GCAP戦闘機はどこが凄い?
GCAPで開発されるのは、「第6世代戦闘機」と呼ばれるものです。現在最新鋭と言われるF-35などが「第5世代」ですから、さらにその先を行く性能を目指しています。具体的にどんな能力を持つ可能性があるのでしょうか?
- さらに進んだ「ステルス性能」
-
敵のレーダーからもっと見つかりにくくなります。まるで“忍者”のように、相手に気づかれずに任務を遂行する能力が高まります。
- 戦場のすべてを把握する「センサーとネットワーク」
-
搭載する高性能センサー(目や耳にあたる部分)で集めた情報を、AIが瞬時に分析。その結果を、他の戦闘機や艦船、地上の部隊、さらには味方の無人機とリアルタイムで共有します。これにより、まるで戦場全体を上空から見渡すような感覚で、最適な攻撃や防御を行う「チームプレイ」が可能になると期待されています。
- パイロットを助ける「AI(人工知能)」
-
複雑な戦況の判断や、膨大な情報の処理、機体の操作などをAIがサポートし、パイロットはより重要な判断に集中できるようになります。状況によっては、AIが自律的に判断して行動する場面も出てくるかもしれません。
- 「無人機(ドローン)」との連携プレー
-
パイロットが乗る有人戦闘機がリーダーとなり、複数の無人機を引き連れて編隊を組みます。危険な任務は無人機に任せたり、より広い範囲を偵察させたりと、有人機と無人機がそれぞれの得意なことを活かして協力する戦い方(有人・無人チーミング)が当たり前になるかもしれません。
- 将来も進化し続ける「柔軟な設計」
-
新しい技術が登場しても、比較的簡単に機能を追加したり、性能をアップデートしたりできるように、ソフトウェア中心の柔軟な設計(オープンアーキテクチャ)が採用される見込みです。これにより、長く第一線で活躍し続けることができます。
GCAPの意義:単なる戦闘機開発を超えて
このGCAP計画は、単に新しい戦闘機を手に入れる、というだけではありません。
- 日本の防衛力の根幹を支える
-
将来にわたって日本の空を守るための基盤となります。
- 国際協力の新しい形
-
日英伊という、基本的な価値観を共有する国々との安全保障協力が深まります。これは、日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」構想とも連動し、欧州のパートナーと共に地域の平和と安定に貢献していく姿勢を示すものです。
- 日本の技術力を守り、育てる
-
戦闘機開発には、材料、エンジン、電子機器など、様々な分野の最先端技術が必要です。GCAPに主体的に関わることで、日本の航空宇宙産業の技術力を維持・向上させ、将来に繋げていく狙いもあります。
- コストとリスクの分担
-
何兆円とも言われる巨額の開発費と、開発に伴う様々なリスクを、3カ国で分担することができます。
まとめ
GCAPは、日本の将来の安全保障を左右する極めて重要なプロジェクトです。同時に、それは国際社会の変化の中で日本が選択した、新しい国際協力の形でもあります。この巨大プロジェクトは、果たして計画通りに進むのか? そして、世界にどのような影響を与えていくのか?
次回は、なぜ日本は長年のパートナーであるアメリカではなく、イギリス、イタリアとの共同開発を選んだのか? その背景にある様々な理由や戦略について、詳しく掘り下げていきます。
第2話:なぜアメリカではなかったのか? ~F-2後継機、日英伊協力へ至る道~
画像出典:防衛省・自衛隊ウェブサイト(https://www.mod.go.jp/j/policy/defense/nextfighter/index.html)公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)