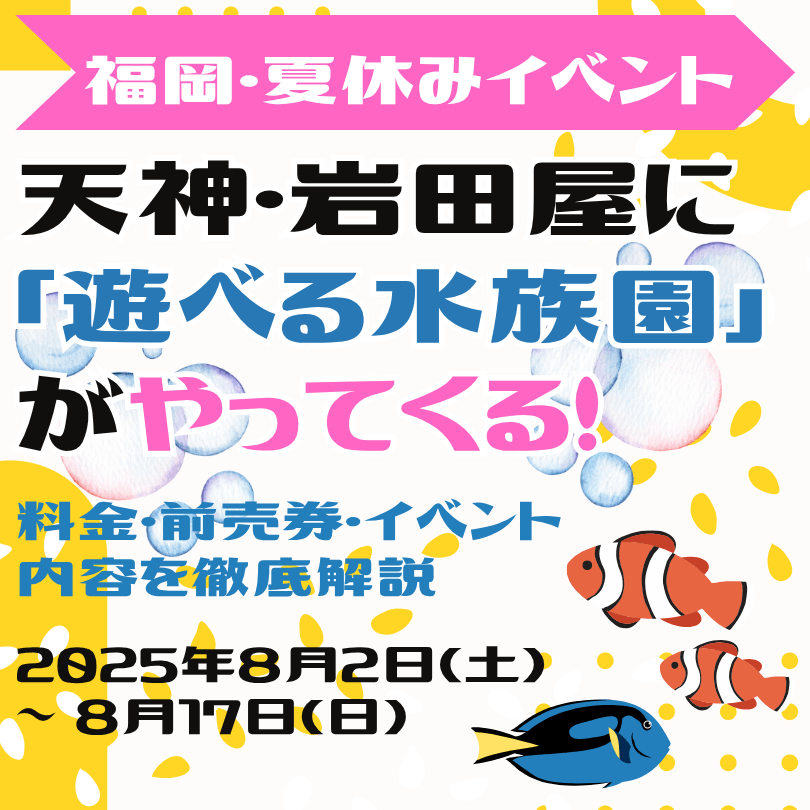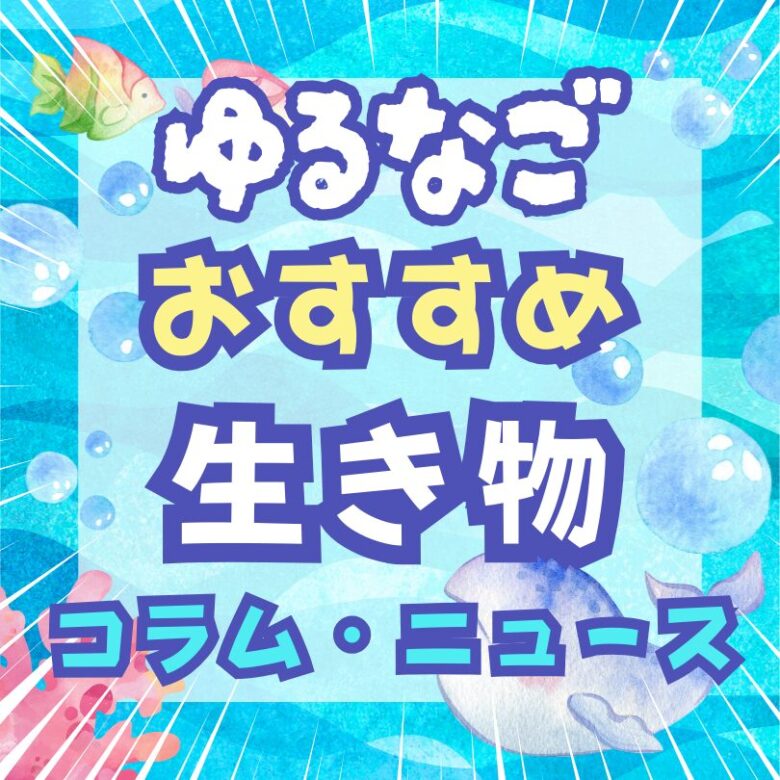東京の漁業が直面する課題と新たな一手
近年、東京の漁業は気候変動の深刻な影響を受けています。海面・内水面を問わず漁業生産量は減少傾向にあり、特に内水面養殖業では水温上昇やゲリラ豪雨による濁水など、飼育環境の悪化が懸念されています。
このような状況に対応するため、東京都は「2050東京戦略」の一環として「持続可能な農林水産業の確立」を掲げ、主要施策の一つとして陸上養殖のビジネスモデル創出を目指しています。
そして2025年9月26日、東京都とNTT東日本株式会社は、この課題解決に向けた「漁協運営型陸上養殖プロジェクト」に関する基本協定を締結しました。これは2025年度から2029年度までの5か年事業として、東京ならではの陸上養殖モデル構築を目指す大規模な取り組みです。
「東京型陸上養殖モデル」の特長と収益性
本プロジェクトの最大の特長は、NTT東日本グループが持つICT(情報通信技術)と連携した「閉鎖循環式陸上養殖プラント」の活用です。
1. ICTによる安定した生産環境
プラントにはICTを活用した飼育管理環境が実装され、遠隔地からの飼育指導機能も導入されます。これにより、気候変動に左右されない生産力の安定化と、効率的な飼育ノウハウの獲得を目指します。
2. 高収益化への挑戦:ヤマメの海水養殖
地価が高い東京で事業採算性を確保するため、プロジェクトは高収益な養殖技術の開発に挑みます。具体的なターゲットとして挙げられているのが、淡水魚であるヤマメです。
実証実験では、このヤマメを海水で飼育し大型化させる技術開発に取り組み、通常の養殖よりも高い収益性を追求します。
3. 高齢者にも配慮した労働環境
さらに、ICTやIoTを活用することで、高齢者なども含めた多様な担い手が働きやすい、労働環境の創出も重要な検討事項とされています。
地域振興と特産品化への具体的な取り組み
プロジェクトは、単に魚を養殖するだけでなく、大消費地である東京の地の利を最大限に生かし、地域活性化に繋げることを目的としています。
多摩地域の特産品化へ
養殖魚の生産後は、事業の採算性を高めるため、地域の企業と連携した商品開発、加工、そして販路開拓にも取り組みます。特に、この取り組みを通じて、多摩地域の新たな特産品化が図られる予定です。
プロジェクトがもたらす効果
東京都とNTT東日本は、この「東京型陸上養殖モデル」の仕組み化を通じて、以下の4つの効果を推進し、持続可能な水産振興と地域振興につなげるとしています。
- 漁協の生産量向上・出荷額の拡大
- 関係人口の増加
- 関連産業への経済波及
- 次世代の担い手育成による漁協経営の安定
【ニュースソース】
東京都とNTT東日本が漁協運営型陸上養殖プロジェクトに関わる基本協定を締結 | お知らせ・報道発表 | 企業情報 | NTT東日本
あわせて読みたい「水と、いきもの」の記事
水槽の中に広がる、もう一つの世界へ。あなたの日常を癒す、美しい魚たちとの出会いが待っています。
-

【夏休み2025・福岡】天神・岩田屋に「遊べる水族園」がやってくる!料金・前売券・イベント内容を徹底解説
-

水と、いきものの世界|水族館・イベント情報と飼育の楽しみ方
-

【速報】東京の漁業が変わる!NTT東日本と東京都が陸上養殖プロジェクト開始。ヤマメの海水養殖、特産品化の狙いを詳しく解説
-

【速報】AQUAism2025Autumn 開催決定!日程やアクセス、チケット情報まとめ
-

【ムクドリ問題・集中連載 第2回】なぜ都市へ? ビル壁、街路樹、安全なねぐらという引力
-

【ムクドリ問題・集中連載 第1回】都市の喧騒、田園の静寂 ~あなたの知らないムクドリの真実~