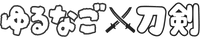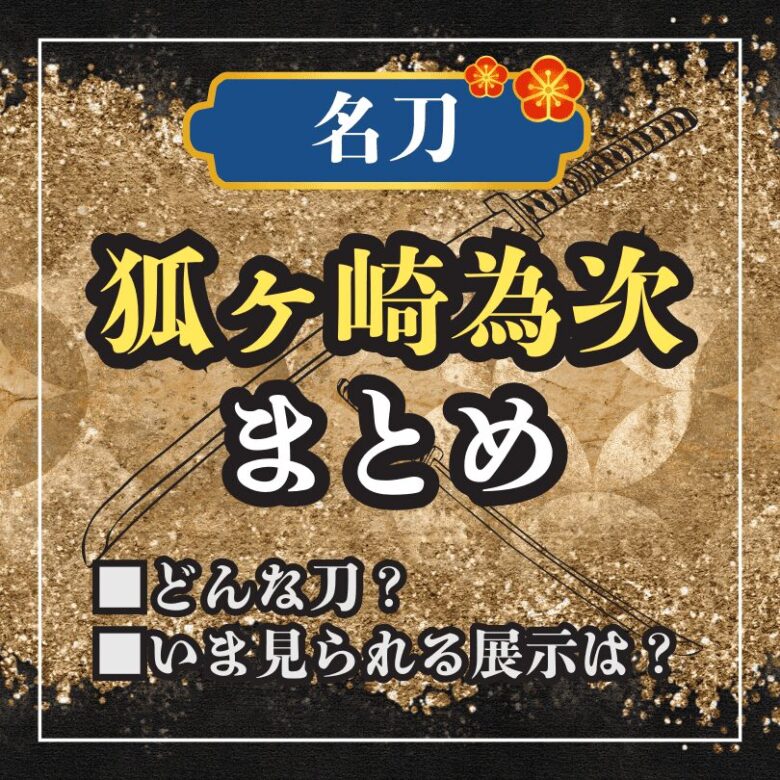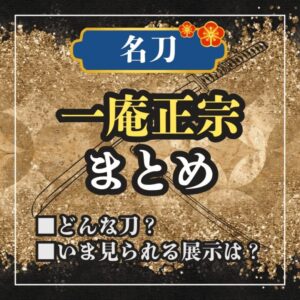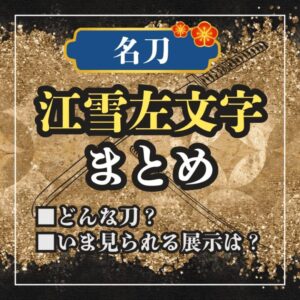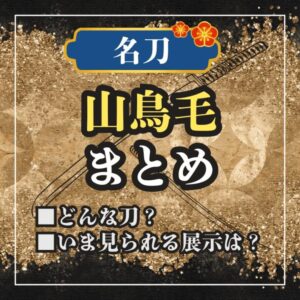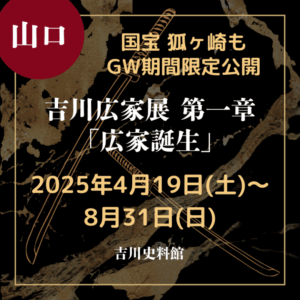1. はじめに:国宝 太刀「狐ヶ崎為次」とは
鎌倉時代初期、備中青江派の名工・為次(ためつぐ)によって鍛えられ、歴史的な一場面と共にその名を刻む国宝の太刀、「狐ヶ崎為次(きつねがさき ためつぐ)」。 正治二年(1200年)、梶原景時一族討伐の舞台となった駿河国狐ヶ崎で、鎌倉幕府御家人・吉川友兼(きっかわ ともかね)がこの太刀を佩き、武功を挙げたことにその号は由来します。 さらに特筆すべきは、刀身のみならず、附(つけたり)として「黒漆太刀拵(くろうるしたちごしらえ)」も国宝に指定されている点です。当時の実用的な武士の拵えが、刀身と共に約800年もの間、吉川家によって家宝として守り伝えられてきたという事実は、奇跡的と言っても過言ではありません。 現在は山口県岩国市の吉川史料館に収蔵されるこの名刀について、刀工・為次と古青江派、詳細な姿と鑑定、号の由来となった歴史的背景、そして現代までの伝来と展示情報をまとめます。
2. 刀工 為次と古青江派
狐ヶ崎為次の作者である為次は、鎌倉時代初期(13世紀前半頃)に備中国(現在の岡山県西部)で活躍した刀工です。平安末期から鎌倉中期にかけて高梁川下流域を拠点とした古青江派(こあおえは)に属します。 古青江派は、同時代の備前国の刀工たちとは異なる独自の作風を発展させました。
- 地鉄(じがね): 杢目肌(もくめはだ)や板目肌(いためはだ)が主体で、「縮緬肌(ちりめんはだ)」と呼ばれる独特の肌合いや、「澄肌(すみはだ)」と呼ばれる黒みがかった鉄の色が見られることがあります。刃文に沿って影のように見える「映り(うつり)」(特に乱れ映りや地斑映り)が現れるのも特徴です。
- 刃文(はもん): 直刃(すぐは)調、または緩やかな波形の浅い湾れ(のたれ)に、小乱(こみだれ)が交じるのが典型的です。小沸(こにえ)出来を主体とし、足(あし)や葉(よう)といった働きが入ります。
古青江派の作風は、古備前派などと比較すると、やや地味ながらも渋く、落ち着いた味わいを持つと評されます。為次はこの古青江派を代表する刀工の一人であり、「狐ヶ崎」はその最高傑作とされています。
3. 狐ヶ崎為次の姿と魅力
国宝「狐ヶ崎為次」は、古青江派と為次の特色を示し、鎌倉時代初期の太刀として極めて高い完成度を誇ります。
【基本情報】
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 種別・指定 | 太刀 ・ 国宝 (附 黒漆太刀拵) |
| 銘 | 為次 |
| 号 | 狐ヶ崎 (きつねがさき) |
| 刀工 | 為次 (備中) |
| 刀派 | 古青江派 (こあおえは) |
| 時代 | 鎌倉時代初期 (13世紀初頭) |
| 刃長 | 約78.5 cm ~ 78.8 cm |
| 反り | 約3.4 cm |
| 元幅 | 約3.1 cm ~ 3.2 cm |
| 先幅 | 約2.1 cm |
| 鋒長 | 約3.3 cm |
| 現在の所蔵 | (公財)吉川報效会(吉川史料館 保管) |
【各部の特徴】
- 姿: 全体として長大で堂々とした太刀姿。反りが深く(約3.4cm)、特に腰元で強く反る「腰反り」が美しい、鎌倉初期の典型的な太刀の姿です。元幅が広く先がやや狭まり、「踏ん張り」がある優美さも兼ね備えています。切先は力強い「猪首切先(いくびきっさき)」。地刃ともに健全な状態が保たれています。
- 鍛え(地鉄): 小板目肌(こいためはだ)がよく詰んでいます。古青江派の特徴とされる縮緬肌とはやや異なりますが、肌立ち気味で「乱れ映り」が鮮やかに立つ点は同派の特徴と一致します。地沸(じにえ)は厚くつき、地景(ちけい)も見られます。
- 刃文: 小乱(こみだれ)を基調とし、小丁子(こちょうじ)が交じります。足(あし)、葉(よう)といった刃中の働きが頻りに入り、複雑な景色を見せます。小沸(こにえ)出来で、匂口(においぐち)はやや締まりごころ(または沈みごころ)と評される古雅な趣があります。
- 帽子(切先): 切先の刃文は沸崩れ(にえくずれ)となっています。切先の強度を高めようとした当時の工夫が見られます。
- 茎(なかご): 作刀当時の姿を留める「生ぶ茎(うぶなかご)」である点が極めて貴重です。これにより、本来の姿や重心、銘の位置などを知ることができます。茎の反りは強く、鑢目(やすりめ)は青江派の特徴とされる大筋違(おおすじかい)。目釘穴は一つ。佩裏(はきうら)の棟寄りに「為次」の二字銘が切られています。
- 拵(こしらえ): 附(つけたり)として国宝指定されている「黒漆太刀拵」は、鎌倉時代の武士が用いた実戦的な様式を伝える貴重なものです。華美さより機能性を重視した質実剛健な作りで、当時の武士の装備を知る上で重要です。
4. 号の由来:梶原景時の変と吉川友兼
この太刀が「狐ヶ崎」と呼ばれる由来は、鎌倉時代初期の歴史的事件「梶原景時の変」(正治二年/1200年)にあります。
源頼朝の死後、鎌倉幕府内で権力闘争が起こり、有力御家人であった梶原景時は失脚し、一族を率いて京都へ向かいました。その途上の駿河国狐ヶ崎(現在の静岡県静岡市清水区付近)で、幕府の追討軍と衝突します。 この戦いに参加した鎌倉幕府御家人・吉川友兼(きっかわ ともかね)が、この為次作の太刀を佩いて奮戦し、景時の三男・景茂を討ち取ったと伝えられています。 この武功と戦場の地名を記念して、友兼の佩刀は「狐ヶ崎」と名付けられ、吉川家の家宝となりました。鎌倉幕府の公式記録『吾妻鏡』にも、景時が友兼を「駿河国一の勇将」と評した記述があり、この伝承の歴史的背景を裏付けています。
5. 吉川家伝来と国宝指定
「狐ヶ崎為次」は、梶原景時の変以降、約800年以上もの間、一貫して吉川家によって家宝として継承されてきました。長期間単一の家系で所有され続けたことが、刀身・拵ともに良好な保存状態に繋がった大きな要因です。 近代に入り、その文化財的価値が認められ、昭和8年(1933年)に旧国宝(現・重要文化財)に、そして戦後の昭和26年(1951年)に文化財保護法に基づく国宝(新国宝)に指定されました。
現在は、吉川家の文化財を保存・公開する公益財団法人吉川報效会が所有し、山口県岩国市にある吉川史料館にて大切に保管・展示されています。
6. 展示情報:狐ヶ崎為次に会える場所
国宝「太刀 銘 為次(狐ヶ崎)」は、山口県岩国市の吉川史料館にて、主に秋季の展覧会などで定期的に公開されています。
- 吉川史料館 公式サイト: https://www.kikkawa7.or.jp/
以下に、当サイト「ゆるなご刀剣」で紹介した、近年の主な展示情報(予定含む)へのリンクをまとめます。
【近年の主な展示履歴】
- 戦国の庭歴史館における写し展示
- 2025年5月5日~6月22日の期間限定で特別公開。
- 【広島・刀剣展示】戦国の庭歴史館「狐ケ崎写し」と安芸太田町 県重文太刀を展示(2025/5/5~6/22)
- 2025年4月19日(土)~8月31日(日) @ 吉川史料館(山口県)
- 吉川広家公没後400年記念展 第一章「広家誕生」にて、4月29日(火・祝)~5月6日(火・休)の期間限定で特別公開されました。(※期間終了)
- あわせて読みたい 【山口・刀剣展示】【2025/4/19~8/31】国宝 狐ヶ崎も期間限定公開(4/29~5/6)!吉川史料館で吉川広家展 第一章「広家誕生」開催
- (吉川元長展における写し展示)
- 2024年秋~2025年4月13日まで開催された「吉川元長」展では、「狐ヶ崎為次」の写しが展示されていました。(※期間終了)
- あわせて読みたい 【山口・刀剣展示】吉川史料館「吉川元長」展で短刀 信国と狐ヶ崎写しを展示 (~4/13)
【注意】 展示期間や内容は変更される可能性があります。必ず会場の公式サイトで最新情報をご確認ください。
7. まとめ:歴史を繋ぐ国宝
国宝「太刀 銘 為次(狐ヶ崎)」は、鎌倉時代初期の備中青江派の名工・為次による、刀身・拵ともに国宝指定された極めて貴重な一振りです。「梶原景時の変」という歴史的事件と、佩用した吉川友兼の武勲に由来する号を持ち、約800年もの間、吉川家に大切に受け継がれてきました。 その優美かつ力強い姿と、歴史的な背景は多くの人々を魅了し続けています。現在は山口県の吉川史料館に収蔵され、定期的に公開されています。
▼国宝指定の刀剣 展示情報・解説まとめはこちら!
国宝刀剣 展示情報・解説まとめ
▼山口県の他の刀剣展示・イベント情報はこちら!
山口県 刀剣展示・イベント情報まとめ