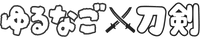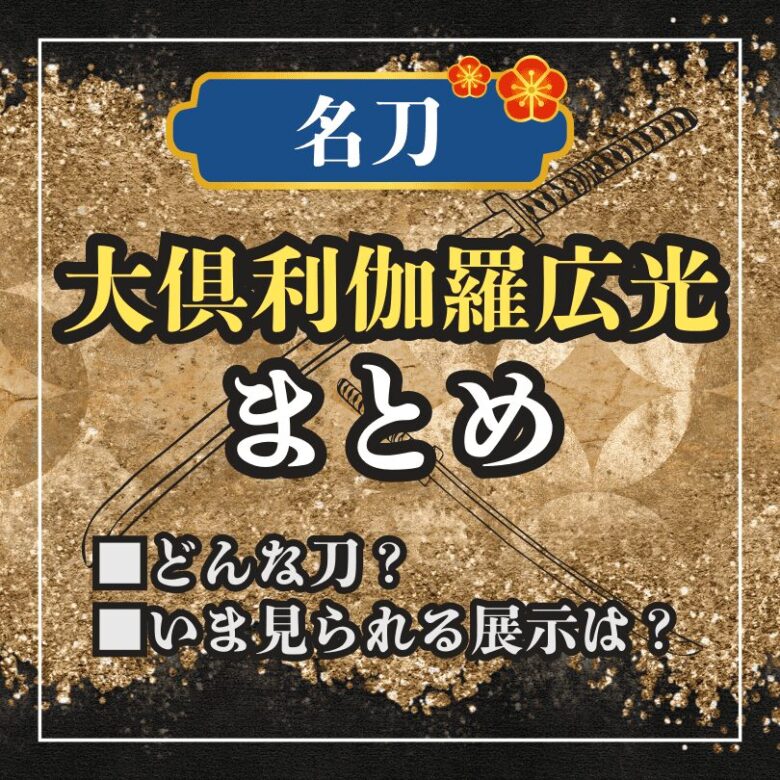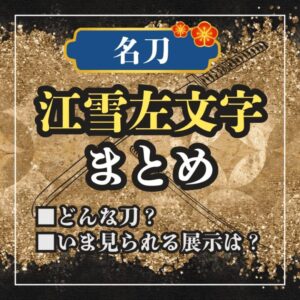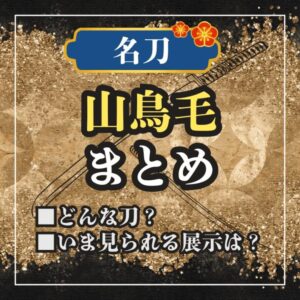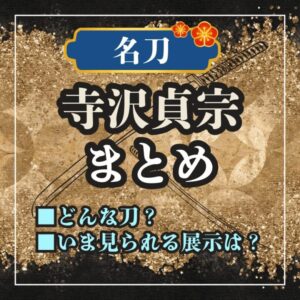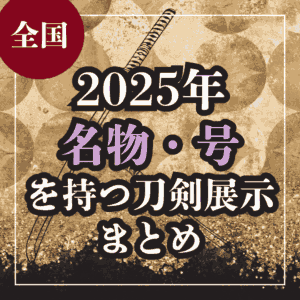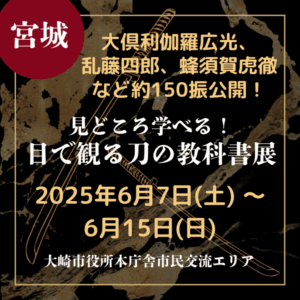はじめに:伊達家伝来の名刀、大倶利伽羅広光
その刀身に力強く彫られた「倶利伽羅龍(くりからりゅう)」の姿からその名を得た、「大倶利伽羅広光(おおくりからひろみつ)」。鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した相州伝(そうしゅうでん)の名匠・広光(ひろみつ)の作と伝えられる、重要美術品指定の刀です。 奥州仙台藩主・伊達家に長く伝来し、その威光を象徴する一振りとして珍重されてきました。現在は個人所蔵となり、日本刀剣博物技術研究財団の管理のもと、大切に保管されています。 この記事では、数々の逸話にも彩られた名刀・大倶利伽羅広光について、その基本情報から刀工・広光と相州伝、号の由来となった彫刻、伊達家を中心とした詳細な伝来、そして現在の展示情報までをまとめて解説します。
刀工・広光と相州伝
大倶利伽羅広光の作者とされる広光は、鎌倉時代末期から南北朝時代初期(14世紀頃)にかけて、相模国鎌倉で活動した刀工です。相州伝の祖・新藤五国光に連なる系譜で、正宗(まさむね)や貞宗(さだむね)に続く世代の代表工とされています。(正宗の門人、あるいは子や養子とも伝わりますが、正確な関係は定かではありません。) 広光が活躍した時代は、蒙古襲来(元寇)を経て、より実践的で強靭な刀剣が求められた時期と重なります。広光も属した相州伝は、硬軟の鋼を組み合わせる鍛錬法により、力強く華やかな作風でこの時代の需要に応えました。 広光の他の代表作には、重要美術品の脇差「火車切(かしゃぎり)」などがあります。
大倶利伽羅広光の姿と特徴
重要美術品に指定されている大倶利伽羅広光は、元は太刀であったものが後世に磨り上げられ、現在は「刀」として分類されています。その姿と作風には、相州伝と広光の特徴が表れています。
【基本情報】
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 種別・指定 | 刀 ・ 重要美術品(昭和9年指定) |
| 銘 | 無銘 (伝 広光) |
| 号 | 大倶利伽羅広光 (おおくりからひろみつ) |
| 刀工 | 広光 (相州) |
| 時代 | 南北朝時代 (14世紀中頃) |
| 刃長 | 67.6 cm (二尺二寸三分 ※重美指定時) |
| 反り | 1.36 cm (四分五厘 ※重美指定時) / 1.7cm説あり |
| 形状 | 鎬造、庵棟、大磨上無銘 |
| 現在の状況 | 個人所蔵(日本刀剣博物技術研究財団 管理) |
号の由来:倶利伽羅龍の彫刻と不動明王信仰
本刀を最も特徴づけ、号の由来ともなっているのが、刀身の表(佩表)に大きく彫られた「倶利伽羅龍(くりからりゅう)」です。不動明王の化身であり、その持つ三鈷剣に黒龍が巻き付く姿を現したこの意匠は「剣巻龍」とも呼ばれ、非常に力強い印象を与えます。倶利伽羅龍は、戦勝祈願や除災招福を願う武士たちの間で篤く信仰された不動明王の象徴です。近年の科学分析により、この彫刻は作刀とほぼ同時代の、広光自身(または同工房)によるものと考えられています。単なる装飾ではなく、不動明王の加護を宿す「守護刀」としての役割が、製作当初から意図されていた可能性を示唆しています。
伊達家への伝来と象徴性
大倶利伽羅広光が伊達家のものとなったのは、江戸時代初期のことです。
- 拝領の経緯: 元和6年(1620年)、仙台藩主・伊達政宗が行った江戸城本丸石垣修復工事の功績に対する褒賞として、二代将軍・徳川秀忠から、政宗の嫡子・伊達忠宗へ下賜されました。(政宗自身が受け取ったわけではなかったようです)
- 伊達家での扱い: 以降、仙台伊達家の至宝として江戸藩邸などで厳重に保管され、その価値も拝領時の「五十枚」から後に「百枚」へと引き上げられました。豪華な打刀拵(黒漆鞘、赤銅金覆輪鍔、後藤光乗・宗乗作の金具など)が付属していたことも記録されています。
- 下賜の象徴性: 将軍家から有力外様大名である伊達家へ、不動明王の加護を象徴する倶利伽羅龍が彫られたこの名刀が贈られたことは、伊達家の功績と忠誠を認め、幕府との良好な関係を示す重要な政治的意味合いを持っていたと考えられます。
【伊達家伝来 略年表】
| 年代(西暦) | 出来事 | 関連人物 |
|---|---|---|
| 1620年 (元和6年) | 徳川秀忠より伊達忠宗へ下賜 | 徳川秀忠, 伊達忠宗 |
| 1681年 (延宝9年) | 付属金具に後藤家折紙発行 | 後藤光乗, 後藤宗乗 |
| 1778年 (安永7年) | 鑑定価値が百枚に格上げ | |
| 1884年 (明治17年) | 東京の伊達邸へ移管 | |
| 1934年 (昭和9年) | 重要美術品に認定 | 伊達興宗 |
| 戦後 | 伊達家を離れ個人所蔵となる |
6. 逸話と伝承:伊達政宗佩刀説は本当?
「独眼竜」伊達政宗がこの刀を佩いて戦場で活躍した、という逸話が広く知られています。しかし、これは歴史的事実とは異なります。大倶利伽羅広光が伊達家に来たのは1620年であり、政宗の主な合戦(例:大坂の陣 1615年終結)よりも後のことです。 この逸話は、政宗の圧倒的なカリスマ性と、「大倶利伽羅」という刀の力強いイメージが結びつき、後世に生まれたものと考えられます。史実ではありませんが、いかに政宗という人物とこの刀が人々の想像力を掻き立てるかを物語っています。
7. 現在の状況と文化財指定
第二次世界大戦後、伊達家を離れた大倶利伽羅広光は、いくつかの所有者を経て、現在は個人所蔵となっています。 本刀は昭和9年(1934年)に重要美術品に認定されました。これは現在の重要文化財に相当する価値を持つものです。
8. 大倶利伽羅広光に会える場所・展示履歴
個人所蔵であり重要美術品であるため、一般公開の機会は限られています。近年では、日本刀剣博物技術研究財団などが関わる特別展で展示されることがあります。
【今後の展示予定】
- 2025年6月7日(土)~6月15日(日) @ 大崎市役所市民交流エリア(宮城県)
- 「見どころ学べる!目で観る刀の教科書展」にて、名物 乱藤四郎や蜂須賀虎徹などと共に展示予定です。拵(こしらえ)も同時に展示される貴重な機会です。
- あわせて読みたい 【宮城・刀剣展示】【2025/6/7(土)~6/15(日)】大倶利伽羅広光、乱藤四郎、蜂須賀虎徹など公開!『見どころ学べる!目で観る刀の教科書展』
【過去の主な展示履歴】
【注意】 展示期間や内容は変更される可能性があります。必ず主催者の公式サイト等で最新情報をご確認ください。
まとめ:大倶利伽羅が語るもの
重要美術品「刀 無銘 広光(号 大倶利伽羅広光)」は、相州広光作と伝わる南北朝時代の名刀です。刀身に彫られた倶利伽羅龍は不動明王への信仰を象徴し、伊達家に将軍家から下賜されたという輝かしい伝来を持ちます。伊達政宗佩刀説は史実ではないものの、それもまたこの刀が持つ物語性を豊かにしています。 現在は個人所蔵・財団管理のもと大切に保管され、時折公開されています。この一振りは、卓越した刀工の技、武士の信仰、大名家の歴史、そして人々の記憶が交差する、日本の貴重な文化遺産です。